クラリネットを始める多くの人が苦戦するのが「タンギング」。音は出るのに何故か演奏がぼやける、リズムが揃わない…といった悩みは、実はほぼ全員が一度は通る道です。筆者自身も、最初は「タンギングって結局何?」と悩んだ末、数々の練習法を試行錯誤してきました。
この記事では、失敗談も包み隠さず交えながら「タンギング克服のためのステップ」を徹底解説します。
タンギングとは?その役割と重要性
タンギングとは、クラリネットにおける「音の表情づけ装置」のようなもの。楽器からしっかりした“発音”を引き出すための必須テクニックであり、メロディをクリアに、リズムを明確に伝える役目を持っています。
私が中学時代、何となく吹いていた旋律が、タンギングが使えるようになった瞬間から、音が引き締まって聴こえた体験は今も鮮明です。
タンギングの基本動作
クラリネットのタンギングは、「舌先でリードを一瞬だけタッチし、空気の流れを一時的に切ってまたすばやく解放する」動作です。
ただ単に舌を動かすだけではなく、リードから舌を“離す瞬間”に集中する感覚がポイント。昔、舌を力いっぱい押し付けて音がつぶれた経験がありますが、その後“抜く瞬間”に意識を変えただけで音のキレが劇的に変化しました。
後輩に教える時も、「一度、思いきりやさしく離す動きだけ試してみて」とアドバイスしてきました。
タンギングの種類と練習法
シングルタンギング
シングルタンギングは最初に覚えたい“基礎の基礎”。「トゥ」「タ」と小さな声で言うような動きで舌を動かします。
一定のテンポで、四分音符や八分音符ごとに、「息は止めず舌だけ使って区切る」ことを強く意識してください。
筆者推奨の練習は、「録音しながら一発ごとの音の粒や揃い方を自分の耳でチェックする」こと。演奏後に自分の録音を聞いて、“頭の中の出来と実力の差”に気付ける瞬間が、上達への大事なステップです。
練習法(私が実際に効果を感じた方法)
- メトロノームを60に設定し、四分音符で1音ずつ丁寧に吹く
- 息は止めず、舌だけで音を区切る
- 録音して「粒がそろっているか」を確認する
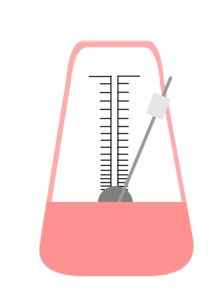
ダブルタンギング
シングルでは追いつかない高速フレーズ用にダブルタンギングを覚えましょう。「トゥカトゥカ」「タカタカ」と声に出しながら舌の先と奥を交互に動かします。
最初は楽器なしでしっかり発音練習、それから実際のスケールに当てはめスピードを徐々に上げていくのが推奨ルートです。
練習法
- まずは楽器を使わず、「トゥク、トゥク」と口で発音して舌の動きを確認する
- 慣れてきたらクラリネットでC dur スケールを使い、ゆっくりからテンポを上げる
私自身、高校時代に吹奏楽コンクールで高速タンギングの壁にぶつかりました。当時は何度やっても指と舌がバラバラ…。
挫折しかけましたが、先生から「10分続ければ必ず変わる」という言葉を信じて“音を伸ばさない”徹底練習を数週間毎日継続することで、なんとか自分のものにできました。
トリプルタンギング
三連符など「3で割るリズム」の際に有効です。「トゥトゥク」や「タタカ」と発音します。
吹奏楽やオーケストラでは頻度は高くありませんが、ソロ曲や特殊なリズムに挑戦する際に役立ちます。
フラッタータンギング
フラッタータンギングは、「舌を使った巻き舌・震え技」で、現代曲やジャズに多く登場する個性的な奏法です。最初は日本語の「るるる…」を巻き舌で発声するイメージから始めてみてください。
私の場合も、家の中や自転車に乗りながら練習して、地道に舌の感覚を鍛えました。成功した瞬間の“ビリビリ感”は、クセになる面白さです。

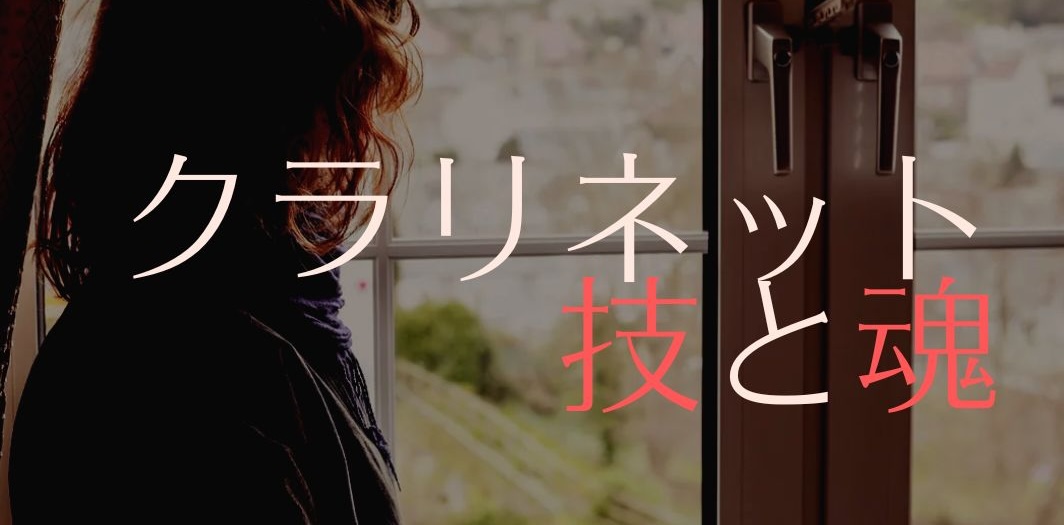

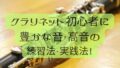

コメント