社会人として働きながらバンド活動を続けることは、時間や体力、そしてメンバー間の調整など、さまざまな課題が伴います。それでも、音楽への情熱を持ち続けることで、10年以上も活動を続けているバンドは少なくありません。
私自身、最初は「仕事と両立できるのか?」と不安な気持ちもありましたが、気づけばもう16年。週末には楽器を抱えてホールや練習室へ。
そんな生活を続ける中で、何度も壁にぶつかりながらも、音楽への情熱があったからこそ乗り越えてこられました。本記事では、私が実際に経験したリアルなエピソードや、長く続けるためのコツを余すことなくお伝えします。

Sc
社会人バンドが抱える課題
時間管理の難しさ
仕事と音楽活動を両立する最大の課題は「時間管理」。バンドメンバーはみなさん、それぞれ仕事を持っていますので、自由に使える時間はバラバラです。
そのため、社会人バンドの練習は、週末の夜間に設定されることが多いです。バンドのHPなどに、定期練習曜日が記載されています。自分が参加しやすい曜日が確認しておきましょう。
結婚されている方、お子様がいる方は、家族の理解と協力が必須です。夜に家を空けるので、家事について事前に話し合っておくことをおすすめします。
結婚後、時間調整については、あまり大変さを感じませんでしたが、子どもが産まれてからは、やはり大変でした。仕事と同じ産休・育休をとりましたが、復帰には、やはり2年は要しました。
夫に負担がかかりすぎないように、練習前に、子どものお風呂を済ませて、食事の準備をしておきました。毎週のことですので、夫だけでなく実家や、夫の家族にもお話をして協力をお願いしたことも。
定期練習以外にも、イベント前には、別途練習が組まれることもあります。私のバンドでは、平日の夜や土日の昼など、低料金で借りられる文化会館の練習室を個人で借り、LINEやGoogleカレンダーを使用してメンバーに知らせます。
参加できる方で集まり、個人練習やパート練習などに活用しています。定例練習にしっかりと参加できない時の補充のための練習として、1時間でも2時間でも練習時間を大切にしています。
こういった努力や調整なしには、継続ができないですが、演奏することの楽しさのため、がんばれています。
体力的な負担
1日働いた後の練習、また演奏会やコンクール時は、体力的な負担も大きくなります。楽器運搬、ステージセッティング、朝早くからのリハーサル、学生の時と違って、何から何まで自分たちで行う必要があります。
日頃から体調管理は必要ですし、無理をし過ぎないことも大切です。
筆者自身、30代後半になってからは、演奏会翌日の「筋肉痛」やら「体の重さ、だるさ」が残るように…。今は翌日の仕事に響くことも。
そこで、毎朝10分だけストレッチを続けることや、筋力を保つため、腹筋やスクワットも10回〜20回行っています。回数は少ないですが、これだけで翌日の疲労感がかなり違います。
メンバー間の意見調整
社会人バンドでは、それぞれ異なる職種や生活環境を持つメンバーが集まるため、意見の食い違いや活動方針についての対立が生じることがあります。
集まって練習をする、だけでは存続はできません。定期的に意見交換や、活動方針などを話し合い、共通の認識を持つことが大切です。
実際、私たちのバンドでも「ライブに出る頻度」や「練習場所」について意見が割れたことが何度もありました。
そんな時は、必ず全員で集まって本音で話し合い、時には飲み会を開いてリフレッシュすることで、チームワークを取り戻してきました。
仕事と音楽活動を両立させる秘訣
明確な目標設定
周りとの調整が必要な活動ですが、それでもみんな「音楽が好き」「楽器を演奏したい」という想いは一つです。その集まりの中で、定期的に目標を設けられると、モチベーションの継続しやすくなります。
大会や定期演奏会、アンサンブル活動など具体的な目標を設定することでモチベーションを維持します。私たちのバンドは、夏のコンクール出演、冬の定期演奏会を大きな柱としています。
それ以外にも、アンサンブル演奏会や、依頼演奏などで小さい目標をつくり、活発に活動できるメンバーと、大きなイベントに向かって活動できるメンバーのバランスもとっています。
- 定期目標:時期が決まっている「大会」「演奏会」の設定
- 不定期目標:地域のイベントや、ホールではなく市民ホールの練習室などを活用したミニ演奏会の実施など
実は、現在のバンドに入る前、高校の先輩、後輩と自分たちでバンドを始めました。仲が良いチームですから、最初はただ集まって吹くだけで楽しかったのですが、楽器のバランスが悪いこともあり。「人前で演奏する」というような目標を定めることができずにいました。
かと言って、新たにメンバーを集める活動もせずにいたため、毎週毎週変わり映えのない活動となってしまい、なんとなく自然解消、というか自然解散、という形となってしまいました。
今となっては、目標とそこに到達するための手段を話し合えなかったことに少し後悔があります。ただ「楽しい」だけでは、なかなか続かないことを実感した出来事でした。
スケジュール管理術
目的:仕事と音楽活動の両方に必要な時間を確保するためにはスケジュール管理が欠かせません。練習に行ってみてとても少ない人数では意味がありません。出欠管理も兼ねて、共有アプリの活用が重要だと思います。
- 週ごとの予定表を作成し、空き時間を明確化する。
- メンバー間で共有カレンダーアプリ(Googleカレンダーなど)を活用して練習日程を調整する。
筆者はGoogleカレンダーで仕事と音楽活動の予定を一元管理しています。これにより、急な予定変更にも対応しやすくなりました。
また、バンドメンバー全員が登録しているLINEグループもあります。定例練習以外で、アンサンブルやパート練をしたい場合のスケジュール調整にも活用しています。
平日に動けるメンバーも把握でき、個人練習やパート練習など、少人数メンバーの練習情報も共有できますので、非常に便利です。

健康管理と体力維持
目的:長時間働いた後でも音楽活動に集中できるよう健康状態を保つことが重要です。
- 毎日の運動で体力維持。
- 栄養バランスの取れた食事でエネルギー補給。
- 十分な睡眠時間を確保する。
筆者は、ジョギングまではできないので、毎晩、腹筋や腕立て伏せなど、シンプルな運動を続けています。一つの運動は20回程度と回数は少ないですが、継続は力なり!です。
また、演奏会が近づいてくると、睡眠もしっかりとるよう心がけ、寝る前と朝、目が覚めた時に、寝たまま腹式呼吸を行うようにしています。
栄養バランスのとれた食事と睡眠、基本的なことが大事だと思います。
社会人バンドを続けるためのポイント
定期的なミーティング
目的:メンバー全員で方向性や目標について話し合い、意識統一を図ります。
また議事録を残しておくこともポイント。後で、決まったことは明確にしておくことが大切です、欠席者に共有もできます。
筆者の経験上、ただ「楽しい」だけでは、続いていきません。「会社じゃないんだから」と面倒に思うかもしれませんが、さまざまな考えの人が集まる団体です。目指す方向や目的を共有することは、存続させるため、とても大切です。
柔軟なスケジュール調整
目的:忙しい社会人生活でも無理なく音楽活動ができるよう柔軟性を持たせます。
定例の練習以外にも、個人練習やパート練習など、自由に参加しやすい練習を設けると、幅広いメンバーに対応できます。
社会人バンドの楽しさ
バンド継続のコツをここまでお伝えしてきましたが、私がなぜ続けることができているかというと、それはやっぱり、楽器を演奏し、仲間と音を重ねる時間が楽しいから!この感覚は、学生時代からずっと変わらない、大切な喜びです。
そしてもうひとつの理由は、「人とのつながり」。社会人バンドでは、年齢も職業もさまざまな人と出会い、音楽を通じて深い絆が生まれます。仕事の肩書きや立場を離れて、同じ「音楽が好き」という気持ちでつながる関係は、本当に貴重です。
忙しい日々の中で、音を合わせ、笑い合う時間は心のリフレッシュそのもの。人生の中で、こんなに素直に夢中になれる時間はそう多くありません。
もし「また楽器をやりたい」「誰かと一緒に演奏してみたい」と少しでも思っているなら、迷わず一歩踏み出してみてください。うまく演奏できなくても大丈夫。音楽が好きという気持ちがあれば、必ず素敵な仲間と出会えます。
私の所属している団体は仲良しで、練習以外でも、だれかの家に集まってホームパーティをしたり、映画を観に行ったりと、楽しく過ごしています。年代も幅広いので、悩みを相談したときにもいろんな角度からの意見が聞けることも、とてもありがたく思っています。
そんな風に、学生時代からの友人とはまた違った、大切な人間関係ができたことも、社会人バンドを続けている理由の一つです。
まとめ
社会人として働きながらバンド活動を続けることは、時間や体力の管理、メンバー間の調整など多くの課題があります。しかし、それらを乗り越えることで、音楽を通じて充実した人生を送ることができます。本記事では以下のポイントをご紹介しました。
- 課題解決:時間管理の難しさ、体力的な負担、メンバー間の意見調整といった課題に対する具体的な対策。
- 両立の秘訣:明確な目標設定、スケジュール管理術、健康管理法など、仕事と音楽活動を両立させるための方法。
- 継続のポイント:定期的なミーティングで方向性を共有し、柔軟なスケジュール調整やオリジナル曲制作で活動を充実させる方法。
社会人バンドは部活とは違い、先生や先輩が引っ張ってくれる活動ではありません。自分たちで考え、決めて、進んでいるパワーが必要です。
苦労は多いですが、その分、学生時代にはない楽しみもたくさんあります。メンバーの結婚式で演奏したり、地域のイベントやお祭りに呼んでいただき演奏するなど、楽しい思い出がたくさん積み重なっていきます。
イベント後の打ち上げを、別日に海の家でのBBQにして、メンバーの家族も参加OKにしたこともあります。これにより、家族の理解も高まりました。
私自身、バンド活動を通じて得た仲間や経験は、人生の大きな財産です。忙しい日々の中でも「音楽があるから頑張れる」と感じる瞬間が何度もありました。この記事が、あなたのバンド活動のヒントになれば嬉しいです。
ぜひ本記事で紹介した方法を参考にして、仕事と音楽活動を両立させながら充実したバンドライフを楽しんでください。

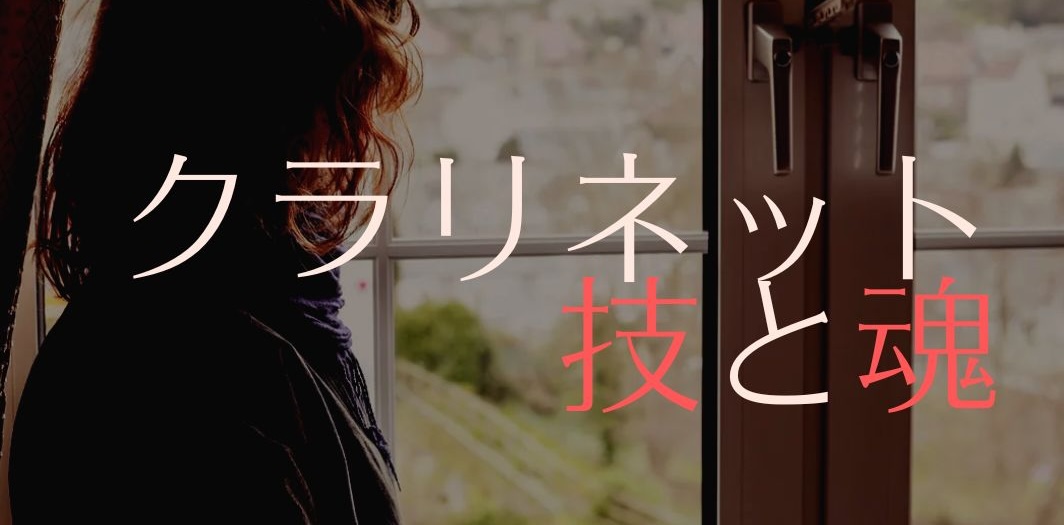
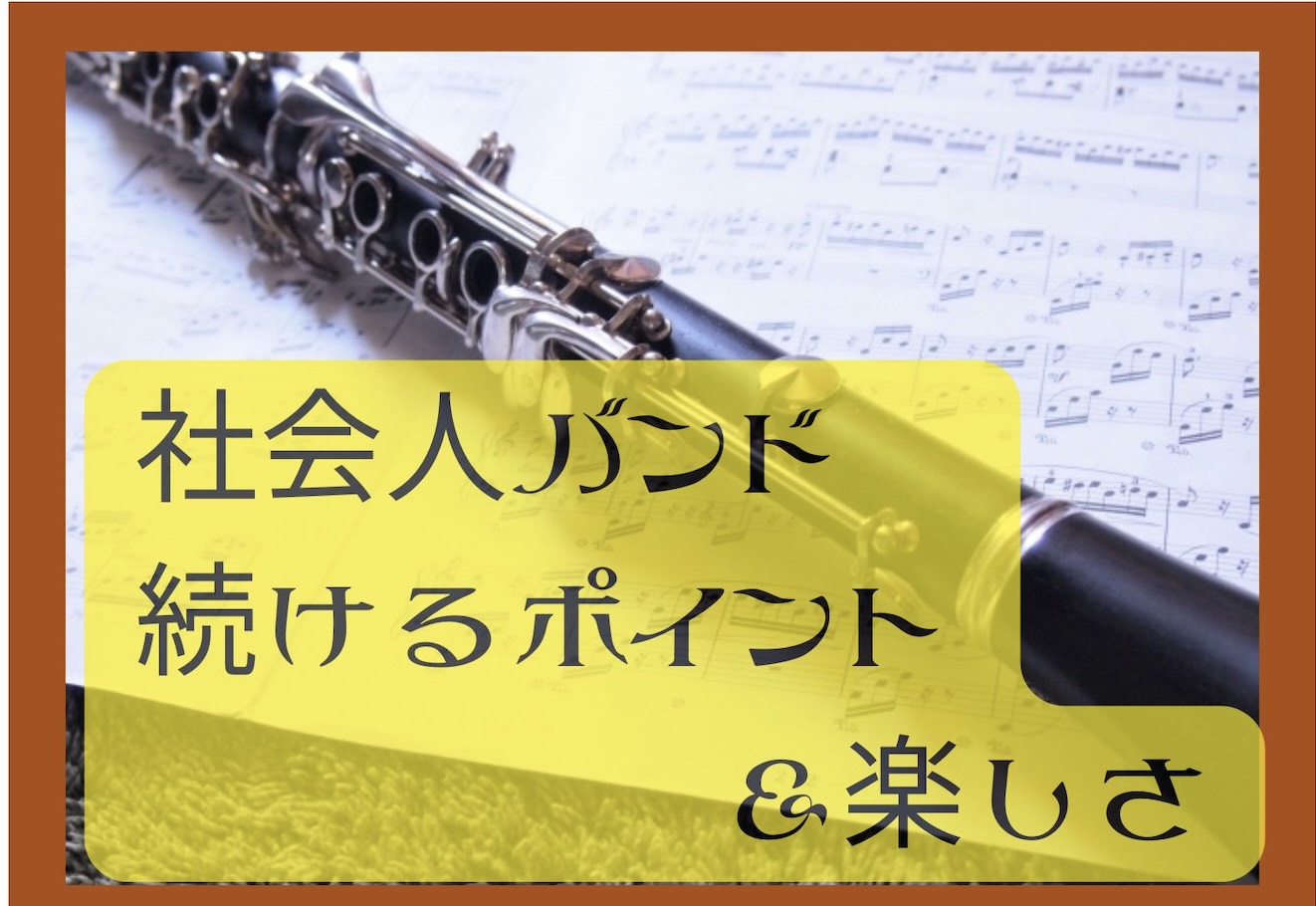


コメント