「高音域になると急に音が細くなる」「どうしても詰まってしまう」「人前で吹くのが怖い」——私がクラリネットを始めたての頃、まさにこの壁にぶつかりました。 中学生時代、部活動で何度も悔しい思いをしたのをいまでも覚えています。
隣の席の友人Yさんは、私とは逆に高音だけはやたら得意で、「なんでそんなに簡単に高い音出るの?」と本気で嫉妬したものです。 しかし、彼女も「実は小さなコツをたくさん実践している」と後から聞いてびっくりした経験があります。
この記事では、私自身の失敗談やうまくいった工夫だけでなく、仲間や生徒のリアルな体験談も織り交ぜて、「高音苦手」を克服するまでのリアルなプロセスをお伝えします。どこかひとつでも「これ、私もやってみよう」と思えるヒントが見つけられる内容を目指しました。
高音域が苦手になる原因とは?
私のこれまでの経験や、仲間の声をもとに「高音域が苦手になる原因」を細かく分けてみました。
息のスピード不足
中学生のころ、初めて参加したクラリネット講習会で、講師の先生が「高音ほど息を速く、細く送る意識が大切」と教えていただきました。私自身は最初、「息が続かなくてつらい」と感じていましたが、先生に教わったストロー練習を続けているうちに、みるみる音が遠くまで伸びるようになったのは驚きでした。
アンブシュアの不安定さ
ある日、練習中に鏡で口の形をじっくり観察してみたところ、思った以上に唇が巻き込まれていたことが判明。「優しく口角を上げるだけ」と言われても、実際にはクセが抜けるまで何日も訓練が必要でした。
また、後輩から「リード噛みすぎて歯が痛くなった」と相談された時、一緒にアンブシュアを矯正したことも今では懐かしい思い出です。 力みすぎ 「ちゃんと音を出さなきゃ…」というプレッシャーで、私もいつのまにか肩がカチカチ、首までガチガチになっていたことが何度も。
そのたびにストレッチや深呼吸を取り入れ、日々の雑談で皆で「今日は絶対リラックス!」と宣言し合ったことは、ユニークな思い出になっています。
私自身、「高音が全然出ない」と落ち込んだ時期がありました。 その時期、練習後に録音して聴き直したら、思った以上に「音が細く、すぐ揺れている」状態。 自分ではうまく吹けているつもりでしたが、初めて問題に気付き、改善に向けて取り組みました。
仲間のA君は、「高音を意識しすぎて無意識に口をすぼめてしまい、余計に出なくなっていた」と話していました。 一方で先輩のBさんは、「高音にこだわらず低音からしっかり身体で響かせる意識をもつようになってから、自然と高音も出やすくなった」と体験を語ってくれました。
こんな風に、人それぞれの壁の乗り越え方やきっかけも実にさまざまです。
高音域を出すための練習法・コツ
レジスターキーを使ったロングトーン
低音から高音まで、同じ息と口の形で吹けるようにすることを目的とした練習です。
練習方法
低い「ミ」を8拍伸ばす(メトロノーム=60で一定に)。
親指でレジスターキーを押して「シ」に移行。このとき息や口を変えないように注意。
2拍休んで形をキープし、次の音へ。
私はこの練習を始めた最初の頃、途中で息が切れてすぐ音がブレることばかりでした。そこで基礎練習に、腹式呼吸の練習もプラス。さらに「1音を10秒かけて鳴らす」ことから始めました。
個人練習の時から、「メトロノームを使って規則的に吹く」ことに変更したところ、不思議と息の流れが安定してきたのを今でも覚えています。
安定した息の流れを保つ
効率よく、安定した息を吹き込むことを目的とした練習です。
ストロー&ティッシュ練習
ストローで思い切り息を吹き出しティッシュペーパーを浮かせる練習です。高音域の鳴り方が自然と良くなった人もいました。「楽器を使わなくてもできるから」と、毎朝5分間だけ自宅で続けていたそうです。
ストローがなくてもできる練習です。最初はけっこう苦しいですが、これで息がバッチリ安定します。
ティッシュペーパー練習を始めた頃、息が続かずすぐティッシュが落ちてしまいました。何度も繰り返し、「お腹から息を押し出す」意識を持つと、安定して長く揺らせるようになり、クラリネットでも息が乱れにくくなりましたよ。
よくある失敗例とその対策
力みすぎて息が詰まる
以前、後輩の女の子が「本番で肩にめちゃくちゃ力が入って全然音が出なかった」と号泣したことがありました。そこで、本番前に皆で一緒にストレッチをしてリラックスする習慣を始めてみたところ、後輩は徐々に高音が出るようになり、私たちも姿勢が整い、息が楽になりました。
アンブシュアが不安定
友人のY君は、毎回口を鏡でチェックし「マウスピースとリードの位置に神経質なくらいこだわるタイプ」。ある日。リラックスして吹いてみたところ、普段よりきれいな高音が鳴り、「肩の力を抜くだけでこんなに違うんだ」と嬉しそうに語っていました。
息のスピード不足
部活動仲間のEさんは、最初「高音を出すためにとにかく息を強くしないと」と思いこんでいました。けれど「息は多さよりもスピードと方向」と知って、ストロー練習を1ヶ月続けたところ、見違えるほど高音が安定したそうです。
高音域克服のための応用練習法
スケール練習で指と息を連動させる
高音域での演奏がぎこちなくなる大きな原因のひとつは、「指の動き」と「息の流れ」がうまく合っていないことです。スケール練習はこの両方を一体化させ、滑らかな演奏につなげるのに最適です。
練習方法
-
C durスケール(ドから高いドまで、)を、メトロノームを四分音符=60程度に設定してゆっくり吹きます。
-
指の切り替えと同時に息のスピードが落ちないよう注意します。
-
慣れてきたら、テンポを少しずつ上げていきます。スピードが速くなっても、指と息がバラバラにならないよう意識することが大切です。
-
上り下りのスケールに加え、三度や四度などの跳躍練習も組み合わせると、さらに応用力がつきます。
私はC durだけでなく、異名同音や半音階スケールもゆっくりと音を確認しながら練習しました。最初は「指に頼りすぎて息が止まりやすい」と気づいてからは、指を動かすたびに流れる呼吸をノートに書いて可視化すると、自然と意識を持てるようになりました。
別のパートの先輩は「部分練習」を勧めてくれ、難しい高音だけを30秒の短いフレーズで繰り返す方法を教えてもらいました。そのおかげで苦手意識が減り、だんだんまとまりのある演奏ができるようになっていきました。
ハーモニクス練習で響きを豊かにする
クラリネットは息の使い方によって音色が大きく変わる楽器です。特に高音では、ただ鳴らすだけだと鋭くなったり、音量が足りなくなったりしがちです。
ハーモニクス練習は、低音と高音を同じ響きにできるよう、楽器全体を共鳴させる感覚を身につけるのに有効です。
練習方法
-
低音の「ド」や「ソ」などをしっかりと響かせてから、その倍音(高い音)に移行します。
-
息のスピードやアンブシュアを無理に変えず、自然な流れで音をつなげることを意識します。
-
音が出にくい場合は、息を少し速めるイメージで支えを強くし、響きの芯を保つことを意識します。
-
慣れてきたら、倍音を何段階か移行させることで、息のコントロール力がさらに高まります。
私は、低音から徐々に倍音へつなぐ練習を日課にしたことで、いきなり高音を吹いても「音が楽に通る」ようになっていきました。低い「ド」からじっくり息を吹き込み、「一段ずつ響きを確かめる」と、音の安定性が増し、よく鳴るように。
本番でも緊張せずに高音に入れるようになりました。
まとめ
クラリネットの高音域は、誰しも必ず一度は悩み、苦労する「成長の壁」だと思います。 ですが「できない」と悩む気持ちを「ちょっと実験してみよう」「今日は違うことを1つやってみよう」と前向きに切り替えた瞬間から、必ず小さな成長が始まります。
私も、友人も、生徒も——最初は全員苦しんでいましたが、地道な試行錯誤で一人ひとり確実に高音を克服していきました。
ぜひ記事で紹介したさまざまな体験談と練習法から、あなた自身に合った上達のヒントを見つけてください。そして「自分のクラリネットでしか出せない音色」を目指して、楽しみながら練習を続けていきましょう!

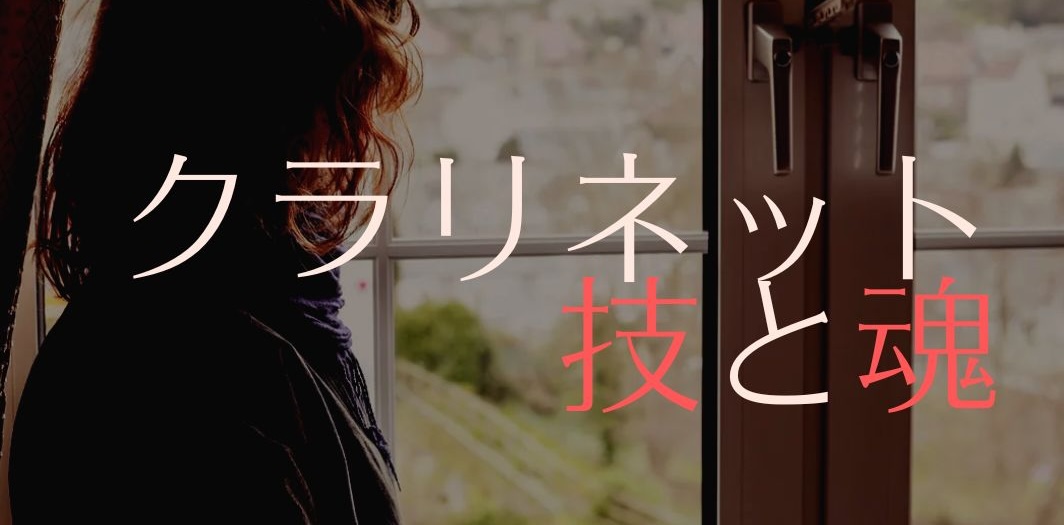
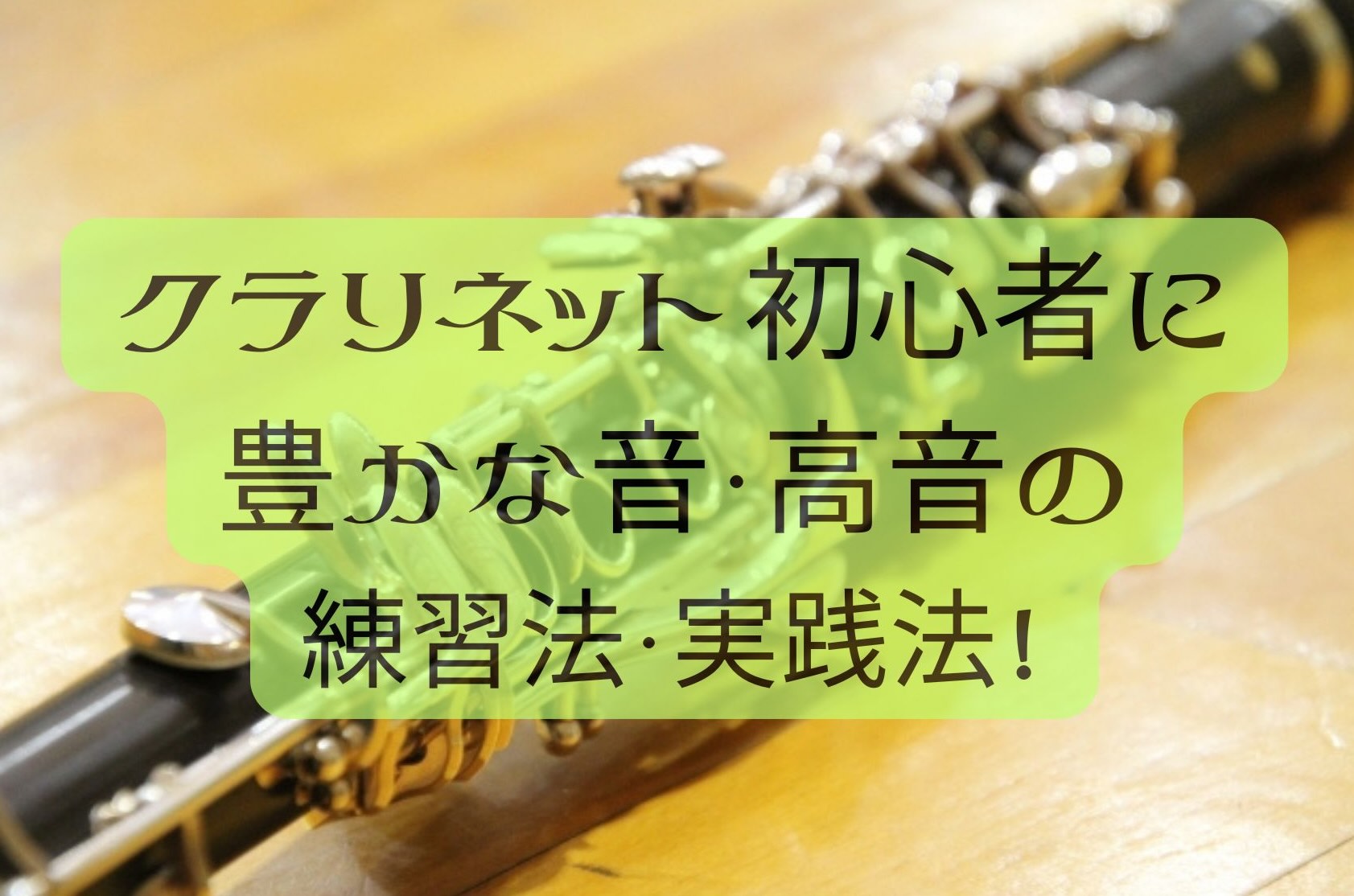
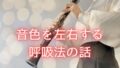

コメント