アンサンブルは「技術を披露する場」だけでなく「仲間とひとつの音楽を作り上げていくプロセス」にこそ魅力があると思います。
私が最初にアンサンブルを経験したのは中学生の頃。自分のパートを必死に追うことで精一杯でしたが、ある時、周囲の音を意識した瞬間に世界が変わりました。
それまでは一方的に音を出していた自分が、まるで仲間と会話をしているように自然にフレーズを受け渡す感覚を得たのです。この「音の会話」を体感したことが、今も音楽を続けている理由のひとつになっています。
この記事では、私自身の経験を交えながら「どうすれば仲間との響きを育て、アンサンブルの中で輝けるか」という練習法を解説していきます。
アンサンブルで調和が重要な理由
音楽の一体感を生み出す
アンサンブルの醍醐味は「一体感の瞬間」にあると思います。
私は以前、クラリネット四重奏で演奏したとき、自分の音が他の楽器と綺麗に溶け合い、音が一方向にすっと流れていく瞬間を経験しました。
その時、鳥肌が立ち「これが調和か!」と実感したのを覚えています。逆に調和を欠いた時は、どれだけ上手く吹いても演奏がバラバラに聞こえてしまう…。
だからこそ、調和を意識することは音楽の「軸」そのものだと感じます。
他パートを引き立てる役割
アンサンブルは主旋が交代していきますので、常に主役でいられるわけではありません。むしろ、自分が脇役に回ったときに音楽はより大きな広がりを持ちます。
大学時代のアンサンブルでは、メロディーを支える役割に徹するパートになったことがあります。演奏中は「地味だな」と感じていましたが、録音を聴き直すと、私の低音の支えがあったからこそメロディーが引き立っていることに気づきました。
その瞬間から「誰かを照らすことで全体が輝く」という意識が芽生え、演奏に対する考え方が一段階広がりました。
チームワークの向上
ひとりの演奏では限界がありますが、仲間と音を聞き合い、合わせることで可能性は無限に広がります。
私が中学の吹奏楽部に入部したばかりのころ、1年生だけで合奏練習をしていたとき、最初は全員が「自分の音だけ正しく吹こう」としてギクシャクしていました。
しかし、何度も繰り返していく中で、互いの音を聴き合う習慣がつくと、不思議なくらい音がまとまり、チーム全体の雰囲気まで良くなっていきました。
音楽を通じてチームワークが育つという体験は、アンサンブルでしか味わえない特別な喜びだと思います。
初心者時代、自分の演奏に集中しすぎて他パートを聴く余裕がありませんでした。練習を録音し、みんなで聴いてみたところ、自分では「うまく吹けた!」と思っていた箇所が、他の音を邪魔していることに気づき、ハッとしました。
それからは、全体の音を聞き、自分のパートの役割を知ること、他パートに耳を傾ける意識をもったことで、演奏がまとまるように変わっていきました。
他パートとの調和を意識した練習法
譜面を読む
- 小節番号をふる(パート、合奏練習の時に重宝)
- 調号・拍子・テンポを確認
- 繰り返し記号やコーダなどの構成をチェック
- 難しそうなリズムや高音、速いパッセージに目をつける
譜面を広げたら、まず「自分はどの役を担うのか」を探します。中学生の頃、私はペンでメロディー部分を赤、伴奏を青、ハーモニーを緑に塗り分けていました。
これだけで自分の立ち位置が明確になり、合奏に入るときに戸惑いが減ります。さらに、調号や拍子を確認し、難しいパッセージには印をつけておきます。こうした地道な作業が、合奏で慌てずに演奏するための下準備になります。
全体像を知る
- 先生や顧問が参考音源を紹介してくれる場合は必ず聴く
- 楽譜からは分かりにくい雰囲気やニュアンスを把握する
個人練習だけでは絶対に見えないものがあります。それは「全体の流れ」です。
私は参考音源を聴くとき、最初は自分の楽器を追いかけますが、2回目以降は自分のパート以外に集中して聴くようにしています。
すると「あ、この場面ではトロンボーンが主導してるんだ」というように、気付くことができます。他のパート、楽器の動きを知ることで、演奏に「寄り添う姿勢」が生まれます。
個人練習の準備
- 指使いが複雑なところは指だけでさらう
- リズムが難しいところは口でカウントしたり、手をたたいて確認
- 書き込み(ブレス位置、指使い、強弱の目印など)をしておく
基礎練習とのつなげ方
- 曲に出てくる音域やリズムを基礎練習に組み込む
- 例えば「三連符が多い曲ならロングトーン後に三連符練習」など
合奏に備える
- 自分のパートが「主旋律」か「伴奏」かを意識しておく(メロディー、伴奏、ハーモニーなど)を確認する。
- 特にメロディーや重要なハーモニー部分に注目し、それらを引き立てる演奏を心掛ける。
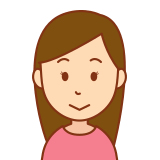
自身の譜面を見ながら、音源を何度も聴きイメージします。具体的に言うと、自分の楽器がどこで旋律を奏でるか、とこで他の楽器の旋律を引き立てる役割をするかをイメージするのです。
譜読みの段階でイメージできていると、合奏にスムーズに入ってけますよ。
内容を入力してください。
アンサンブル・合奏の練習方法
リズムを合わせる
練習方法
- メトロノームに合わせて全員で同じテンポで演奏する練習を行う。
- 楽器を置いて手拍子や、歩いたりスキップするなどして、テンポ感覚を共有する。
高校時代、3拍子のワルツに取り組んだとき、先生に言われたのが「音を出す前に体で感じろ」でした。その方法とは・・・
なんと、先生がピアノでワルツを弾き、それに合わせて全員でステップを踏み、輪になって歩き回ったのです。この練習は今でも鮮明に覚えています。最初は恥ずかしかったのですが、「リズムが体に入る」感覚が楽しくなっていきました。
その後に演奏した時には、全員の足並みが自然に揃い、ワルツのダンス、を表現できたと感じました。演奏がレベルアップし、その年の吹奏楽コンクールで、金賞をとることができました。
リズムを共有するとは、単にテンポを合わせることではなく「体で同じリズムを感じる」ことだと学びました。
ハーモニーを作る
各パート間で美しい和音(ハーモニー)を作り出しましょう
練習方法
- 低音(バス)と高音(ソプラノ)のバランスを整える練習から始める。
- 徐々に中間音(アルトやテナー)も加えながら全体のハーモニーを確認する。
- 録音して聴き返し、バランスや響きをチェックする。
ハーモニー練習で役立ったのは録音です。あるとき、合奏を録音して聴き直したら、自分の音が強すぎて全体の響きのバランスを崩しているように感じました。
その後は「溶け込むように音を出す」意識を持ち、低音や中音の動きに耳を澄ますことを習慣にしました。不思議と、その意識を持つだけでハーモニーが柔らかくまとまり、全体で出す和音が心地よいものに変わっていったのです。
前半にも書きましたが、今は、スマホなど簡単に録音できますから、個人練習の時も録音して聴くことをおすすめします。
アイコンタクトとボディーランゲージ
指揮者がいない、アンサンブル演奏のときは、視覚的なコミュニケーションや、ブレスを合図にタイミングを合わせていきます
練習方法
- 合図を出す人を決めます。
- 演奏中にお互い目線を合わせたり、小さなジェスチャーでタイミングや強弱を伝える練習を行う。
- 特に曲の出だしや終わりなど重要なタイミングではアイコンタクトを徹底する。
アンサンブルでは目の動きが重要な合図になります。私はクラリネット四重奏で「誰が合図を出すか」を決めてはいましたが、それ以外でも演奏中に自然とアイコンタクトが生まれてタイミングが完璧に揃ったことがあります。
その瞬間、言葉を超えた意思疎通ができたようで非常に感動しました。こうした小さな工夫が演奏全体に大きな安心感を生みます。
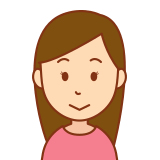
この時のアンサンブルコンテストで、金賞をとることができました!上の大会には進めませんでしたが、「意思疎通」ができている演奏は、聴いている人にも伝わるんだなと感じた経験でした。
よくある失敗例とその改善
失敗例1:自分に集中してしまう
問題点:自分の演奏に集中しすぎると、周囲の音を聴けず、結果として一体感が欠如してしまいます。
改善策:他パートがメロディーを担当している場合は、それを引き立てる演奏を心掛ける。録音を活用して、自分の演奏が全体と調和しているか客観的に確認する。
かつて私は「自分が正確に演奏しなければ」と思いすぎ、全体を聴けない時期がありました。録音を聴き客観的に把握することで改善できました。
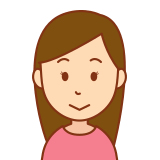
周囲の音に耳を傾ける意識を持つことがポイント
失敗例2:テンポがバラバラになる
問題点:各パートでテンポ感覚が異なると、演奏全体が乱れてしまいます。
改善策:共通のテンポ感覚を養う。とにかくメトロノームで何度も合わせる。微妙なずれは、手拍子をして、それぞれのパートを歌ってみるとか、とにかくテンポ感覚を共有することをおすすめします。
かつて私は「正確に演奏しなければ」と思いすぎ、全体を聴けない時期がありました。大切なのは「メトロノームに合わせる」先にある、周りに合わせるという意識です。
失敗例3:ハーモニーが不協和音になる
問題点:各パートの音程がずれると、美しいハーモニーが作れず、不協和音になってしまいます。
改善策:チューナーを使って音程を合わせることは基本中の基本です。あとは、自分の楽器のくせ(上ずる音はないか?など)、とにかく周りの音をよく聴く、くせをつけましょう。
慣れたらチューナーに頼りすぎずに、周囲の音を「耳で合わせる」練習を取り入れ、自分の音のクセ(特定の音で上ずるなど)を把握したことで安定しました。
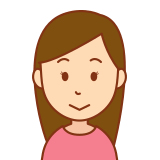
アンサンブルは「耳」を育てる練習にもなります!
アンサンブルを楽しむための心構え

自分の役割の理解
アンサンブルを楽しむには「自分の役割を理解し、自分の音を通じて仲間の音を支える」心構えが必要です。
他パートへのリスペクト
他のメンバーの演奏を尊重し、お互いに支え合う気持ちを持つことで、自然と調和した演奏が生まれます。
チーム全体で楽しむ姿勢
アンサンブルは一人ではなくチーム全体で作り上げるものです。お互いにコミュニケーションを取りながら楽しむ姿勢が、良い演奏につながります。
筆者は中学生のころ、最初にアンサンブルに挑戦した時、思ったようにうまくいかず落ち込みました。そんな時、先輩に「旋律を邪魔せず引き立たせる、ということも、立派な役割だよ」と言われ、気持ちが楽になったことがあります。
その経験から「出す場所と控える場所を知る」ことこそが、アンサンブルを楽しむ秘訣だと学びました。
周りの音を聞き、表に出るところ、引き立て役のところを理解できたとき、演奏が楽しくなりました。
まとめ
アンサンブルは「個人の実力を見せる場」ではなく「仲間と音を共有し、一体感を味わう場」です。
譜面を深く読み込み、体でリズムを感じ、アイコンタクトで心を通わせる…。こうした積み重ねが、響きのある演奏を生みます。私自身も、仲間との演奏を通して音楽がもっと好きになり、自分ひとりでは味わえなかった感動を得ることができました。
ぜひ、あなたも日常の練習に「他者の音を聴く耳」と「共に楽しむ心」を取り入れ、仲間と響きを育ててください。その時間が、きっと一生の宝物になるはずです。
素晴らしいアンサンブル経験があなたの音楽人生をさらに豊かにしてくれることを心から願っています!

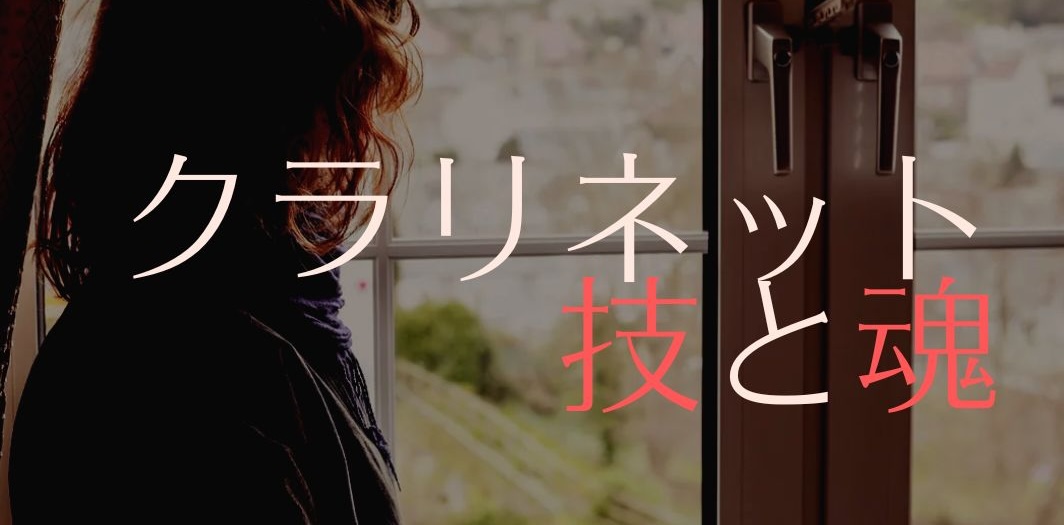
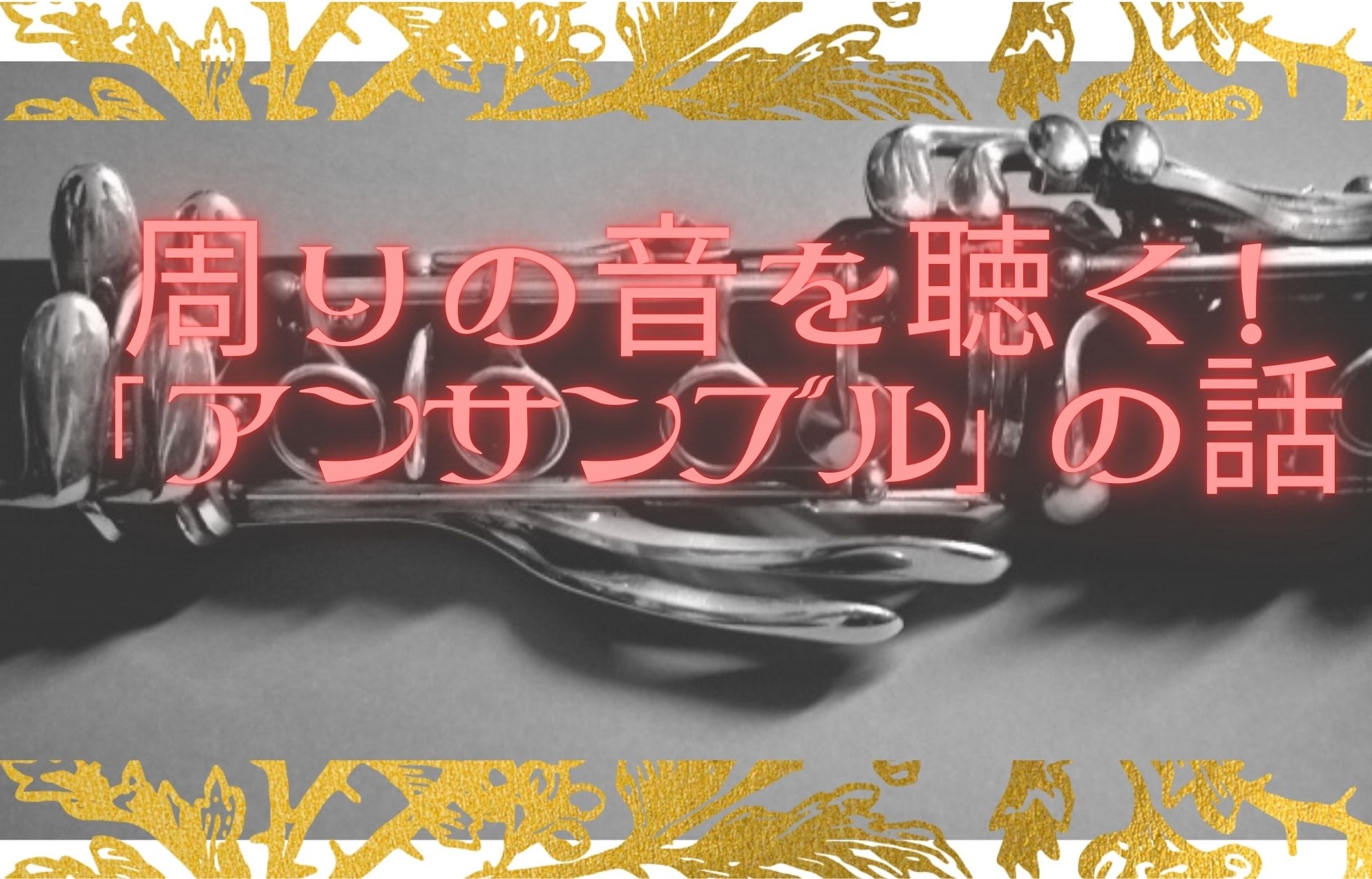

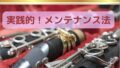
コメント