クラリネットは、吹奏楽やオーケストラ、さらにジャズやポップスに至るまで幅広く活躍する楽器です。特に吹奏楽では、メロディ、オブリガート、ハーモニーと役割が多彩で、常に演奏に参加していることが多いです。
楽譜を見ても、休みが極端に少なく、演奏者としては「吹きっぱなし」と感じる場面が多いと思います。私自身、初めて部活で演奏した際、その忙しさと難易度に驚かされました。
そんなクラリネット奏者にとっては、毎日の基礎練習の中で、スケール練習も外せない練習の一つです。
本記事では、毎日のスケール練習を劇的に効果的にするための練習メニューやコツを詳しく解説します。また、筆者自身の体験談も交えながら、初心者から上級者まで役立つ実践的なアプローチをご紹介します。
スケール練習が重要な理由
クラリネットを始めた人が必ず直面するのが「スケール練習」。基礎の中の基礎と言えるトレーニングですが、ただ音階をなぞるだけでは効果が半減してしまいます。
実はこの練習、指先のコントロール力を磨くだけではなく、音程の安定、音色の表現力、さらには即興演奏にも直結する“総合力アップの近道”です。
つまり、毎日のスケール練習をどう工夫して行うかが、数ヶ月後の上達スピードを大きく左右するのです。
指使いの正確性を向上させる
クラリネットは音域が広く、運指が複雑な楽器です。スケール練習を通して、指の動きを滑らかにし、正確な運指を身につけることができます。
筆者もかつて、連符の多い曲で指がもつれてしまい、思うように演奏できなかった経験があります。そこで、16分音符や3連符、付点リズムなどをスケールに取り入れて練習したところ、指の動きが格段にスムーズになり、曲中の難所にも対応できるようになりました。
音程感覚を養う
スケール練習では、音と音の間隔(インターバル)を身体で覚えることができます。特にクラリネットは音程が不安定になりやすいため、耳と指の連携が重要です。
筆者は、音階を上がるだけでなく、必ず下降形もセットで練習するようにしています。高音から低音へと戻ることで、音のつながりが自然になり、音程の安定感も増しました。
音楽表現力を高める
スケール練習で得た技術は、曲の演奏や即興演奏にも応用できます。ジャズやポップスでは、スケールの知識が即興演奏の基礎となり、自分らしいアレンジを加える際にも役立ちます。
筆者は、スケール練習を通して「音を並べる」だけでなく、「音楽として語る」感覚を身につけることができました。単なる基礎練習が、表現力のある演奏へとつながる瞬間は、何よりも嬉しいものです。
筆者は、中学の吹奏楽部が、「良い演奏をする!」ということを目指すストイックな環境でした。全員が毎日基礎練習をしっかりと行う環境で、周りのレベルも高く、切磋琢磨し、少し緊張感のある環境でした。
高校でも吹奏楽部に入部しましたが、ここは演奏を楽しむといった雰囲気で、優しく、基礎練習を毎日するというような環境ではありませんでした。そんな中、私自身もなんとなく緊張感を失い、2ヶ月ほど、基礎練習をおろそかにしてしまった時期がありました。
すると、演奏中に連符を吹く際に、指がころぶ、全ての音がきれいに出ていないことに気づきました。楽しく、気持ちよく演奏ができないのです。練習は嘘をつかない、と思い知り、後悔した瞬間でした。
それからは、スケール練習も軽んじることなく、しっかりと行っています。
効果的なスケール練習メニュー
スケール練習は、ただ音階をなぞるだけではなく、演奏技術の土台を築くための“音楽的筋トレ”です。以下は、筆者自身が実践して効果を実感した、20分間の集中スケールトレーニングメニューです。
この20分メニューは、単なる音階練習を「音楽的なトレーニング」に変えるための工夫が詰まっています。毎日少しずつでも継続することで、確実に演奏力の底上げにつながります。ぜひ、自分のペースで取り入れてみてください。
基礎練習メニュー(毎日20分)
ロングトーン+スケール昇降
まずおすすめしたいのが「ロングトーンとスケール昇降の組み合わせ」です。スケールをただ吹くだけでなく、1つの音を4拍しっかり息を送り込みながら吹き進めていくと、息の支えやアンブシュア(口の形)の調整が体に定着します。
特にクラリネットは低音と高音で必要な息の圧力が変わるため、スケールを使いながらロングトーンをすることで、音域の切り替えをスムーズにできるようになります。
最初は音がブレても問題ありません。「息と指を同時に整える練習」と考え、毎日5分ほど取り入れるだけで演奏が安定してきます。
リズムのバリエーションを加える
スケールは、8分音符、16分音符、3連符、付点8分音符、シンコペーション(アクセントを裏拍に移動する)などに、リズムを変えて吹くことで、指の柔軟性とリズム感が鍛えられます。
単調になりがちなスケール練習に変化を加えることで、集中力も持続しやすくなります。曲中の複雑なフレーズにも対応しやすくなるため、実践的な効果が高い練習法です。
ダイナミクスの幅を広げる
音量をpp(ピアニッシモ)からff(フォルティッシモ)まで段階的に変化させながらスケールを吹くことで、息のコントロール力と表現力が向上します。音量の変化に合わせてアンブシュアや舌の使い方も調整する必要があるため、より繊細な演奏技術が身につきます。
テンポを段階的に変化させる
メトロノームを使って、テンポ60から120まで徐々にテンポアップしながらスケールを練習します。最初はゆっくりと、音の正確さと指の動きを確認しながら吹き、慣れてきたら少しずつスピードを上げていきます。
速く吹くことが目的ではなく、「正確に吹けるテンポ」を見極めることが大切です。
タンギングの多様化
同じ音を使って、4分音符・8分音符・16分音符・スタッカートなど、さまざまなリズムと音の長さでタンギング練習を行います。舌の動きと息のタイミングを一致させることで、音の立ち上がりがクリアになり、アーティキュレーションの精度が高まります。
応用的なスケール活用
その日の練習曲の中で、特に難しい部分をスケール化して取り出し、集中的に練習します。例えば、連符や跳躍が多いフレーズをスケールに置き換えて吹くことで、指の動きや音程感覚が自然と身につきます。
曲に直結する練習は、モチベーション維持にも効果的です。
最初はとにかく疲れる練習でしたし、スムーズに音階を吹くことができませんでした。しかし、諦めずに、毎日毎日続けていたところ、ある日、いつもつっかえていた運指が、するっときれいにつながるようになったのです!とても嬉しかったです。
それ以降も、楽譜でスムーズにいかない連符があるときは、上記の練習法で、その連符を何度も何度も練習します。私は、付点をつけて何度が吹き、その後楽譜通りに吹いてみると、指が転ばずにスムーズに吹くことができます。
付点の練習、おすすめします。
よくある失敗例とその改善策
スケール練習は地味に見えて、実は奥が深いもの。間違ったやり方で続けてしまうと、思うような成果が得られず、モチベーションも下がってしまいます。よくある失敗例とその対処法をご紹介します。
失敗例1:テンポを上げすぎてしまう
「速く吹けるようになりたい」と思って、いきなりテンポを楽譜通りテンポ(例えば120など)でチャレンジしてしまうケースがあります。
しかし実際は、指がスムーズに動く前にスピードだけ上げても、音が転んだりリズムが乱れたりして逆効果です。
実際に私もこの方法で、以前は手が追いつかなかった16分音符のスケールを、安定して吹けるようになりました。
失敗例2:調性を限定して練習する
CメジャーやGメジャーなど、吹きやすい音階ばかりを繰り返し練習してしまい、♯や♭が多い調性になると指が混乱する。
筆者は、苦手な調性に赤色をつけて記録し、重点的に克服するようにしています
失敗例3:身体の緊張を無視する
集中して練習するあまり、肩や腕に力が入りすぎてしまい、音色が硬くなったり、指がスムーズに動かなくなる。
筆者もこの習慣を取り入れてから、音色が柔らかくなり、長時間の練習でも疲れにくくなりました。
おすすめ教材と活用法
初心者向け:『はじめてのスケール帳』
クラリネットを始めたばかりの方にぴったりの一冊。Cメジャーなど基本的な調性からスタートでき、指使いが図解されているため、楽譜が苦手な人でも安心して取り組めます。
特に便利なのが「練習進捗表」。毎日の練習内容を記録できるので、モチベーションの維持にもつながります。筆者もこの教材を使っていた頃は、進捗表にチェックを入れるのが楽しみで、自然と練習習慣が身につきました。
活用ポイント: ・1日1調性ずつ進めることで無理なく継続 ・指使い図を見ながら、鏡で姿勢チェックをすると効果的
中級者向け:『アイヒラー スケール』
クラリネット奏者の定番教材として知られるアイヒラーは、音大受験生や吹奏楽部の上級生にも広く使われています。
7種類のアーティキュレーション(スラー、スタッカートなど)を組み合わせた練習ができるため、表現力と技術力を同時に鍛えることができます。
筆者も高校時代にこの教材に取り組み、アーティキュレーションの違いによる音色の変化を意識するようになりました。曲の中で「どう吹き分けるか」を考える力がついたのは、この教材のおかげです。
活用ポイント: ・毎週1種類のアーティキュレーションに集中して練習 ・録音して聞き比べると、音色の違いが明確にわかる
上級者向け:『横川晴児 音階と運指』
プロ奏者や音楽大学の学生にも愛用されている、非常に高度な内容を含む教材です。微分音(半音よりさらに細かい音程)まで網羅されており、クラシックだけでなくジャズや現代音楽にも対応できるスケール力が身につきます。
また、ジャズインプロビゼーション(楽譜に頼らず、その場のひらめきや状況に応じて自由に音を紡いでいく、ジャズに欠かせない演奏スタイル)のためのスケール練習法も収録されており、即興演奏を目指す方にもおすすめです。
筆者はこの教材を使ったことで、「スケールが音楽になる瞬間」を体感しました。
活用ポイント: ・調性ごとに難易度を分けて、無理なくステップアップ ・即興練習と組み合わせることで、実践力が飛躍的に向上します。
筆者は初心者時代にアイヒラースキールを使用し、自分のレベルに合わず、挫折してしまった経験があります。現在では「現在の実力+少し挑戦」のレベル感で教材を選ぶことを推奨しています。
スケール練習を曲に活かす!応用テクニック
スケール練習は、ここまでお話ししたとおり、基礎トレーニングではありません。実際の演奏に直結する、大事な練習です。即興、アレンジに応用することで、演奏の幅がぐっと広がります。
ここでは、スケールを“音楽的に使いこなす”ための実践的なテクニックを紹介します。
実際のクラリネット曲に登場するスケール例
クラリネットのレパートリーには、スケールがそのまま使われているフレーズが数多く存在します。例えば、
- モーツァルト《クラリネット協奏曲 第1楽章》 冒頭の上昇スケールは、まさに基礎練習で使う音階そのもの。音の粒をそろえて吹くことで、曲の冒頭から印象的な響きになります。
- 吹奏楽曲《アルメニアン・ダンス》など 急速なスケールの連続が登場する場面では、運指の正確さと音程感覚が問われます。スケール練習で培った力がそのまま活きる瞬間です。
- ジャズアレンジ曲《Sing Sing Sing》など スウィングの王様」と称されたクラリネット奏者・バンドリーダーのベニー・グッドマンの代表曲。筆者も大好きな曲です!即興風のフレーズや装飾音にスケールが多用されており、スケールの技術があるとアドリブにも対応しやすくなります。
ポイント: 曲の中でスケールが使われている箇所を見つけたら、そこだけを取り出してスケール練習として反復することで、演奏の安定感が増します。
難所をスケール化して克服する方法
「このフレーズ、いつも指がもつれる…」という悩み、ありませんか?そんなときは、難所を“スケール化”して練習するのが効果的です。
スケール化の手順
- 難しいフレーズを抽出(例:連符や跳躍が多い部分)
- 音階に置き換える(例:Dメジャーのスケールに近いならDメジャーで練習)
- リズムやテンポを変えて練習(ゆっくり→速く、均等→変化)
筆者も、吹奏楽のソロパートで指が転びがちな箇所をスケールに置き換えて練習したことで、演奏時の安定感が格段に向上しました。スケール練習は、曲の“難所攻略ツール”としても非常に有効です。
即興演奏やアレンジへの応用
ジャズやポップスの演奏では、スケールの知識が即興演奏の基礎になります。たとえば
- ブルーススケール(ブルースらしい響きを生み出すための「ブルーノート」と呼ばれる音「短3度、減5度、短7度」を、既存の音階に加えたもの)を使えば、ジャズ風のアドリブが可能に
- ドリアン・モード(マイナー系のスケールの一種で、ナチュラル・マイナースケールの第6音を半音上げたスケール)やミクソリディアン(メジャースケール(長音階)の第5音を基音とする「ミクソリディアンスケール(旋法)」、または、その旋法でできた和音(コード)のこと)など、モードスケールを使うと、より深みのある即興ができる
コード進行に合わせたスケール選択(コードの響きに合った音を選び、そのコード上で使用できる特定のスケールを選択する)で、アレンジの幅が広がる
筆者は、高校生のころ、ジャズ曲のソロを任されましたが、最初は、どうしていいがわからずに、楽譜にある参考のメロディをそのまま吹いていました。
先生から、「せっかくジャズを吹いているんだから、もっと自由に、遊んでみて。スケール練習のつもりで、少しアレンジしてごらん」と言われ、楽譜のメロディに、スケール風にしてアレンジしたところ、なんとなく雰囲気の出るソロに。
周りにも褒められて、アレンジを増やしたところ、演奏会本番では、好評をいただくことができました。
まとめ
スケール練習は単なる基礎練習ではなく、音楽を自由に操るための“共通言語”です。正確に音を並べる力がつけば、難しい曲の高速フレーズにも対応できますし、即興演奏の場面では自分らしさを表現するための土台になります。
毎日の積み重ねは小さく見えても、数ヶ月後、数年後に大きな違いを生みます。
今日からの練習で「スケールを音楽に変える」一歩を踏み出してみてください。

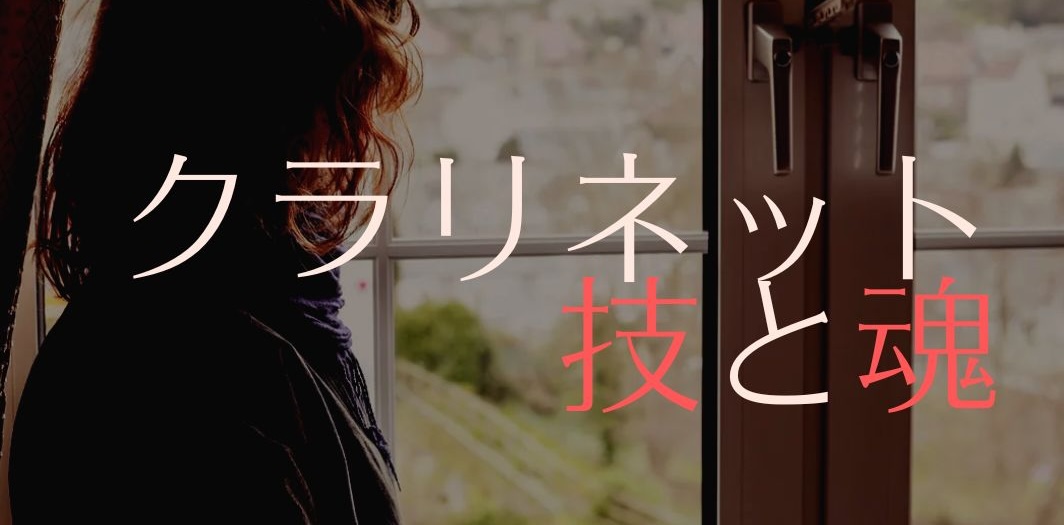
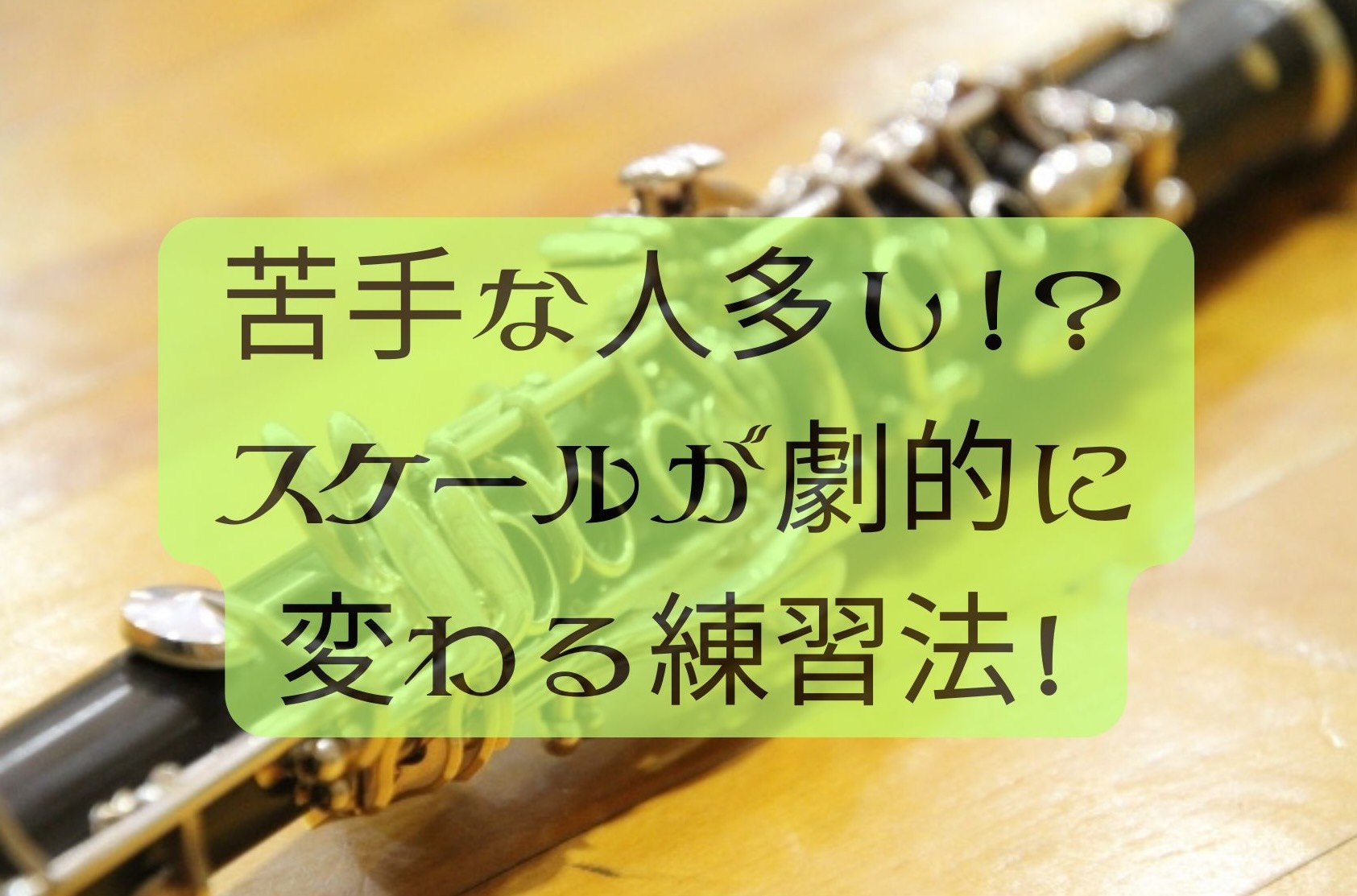

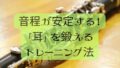
コメント