社会人になってからクラリネットを始めた方、または久々に楽器を再開した方へ。 「最初に練習する曲選びでつまずいた…」「思ったより音が出しづらい」と感じていませんか? 実は、無理なく取り組める曲選びが“挫折しない”最大のコツです。
この記事では、初心者が本当に上達を実感できるおすすめ曲や練習法を、失敗と成功の体験両方を交えながら徹底解説します。読めば“次に何をすればいいか”が必ず分かります!
初心者が最初に選ぶべき曲の基準
馴染みの旋律を選ぶ
例えば子供の頃から耳にしてきた童謡や、テレビ・映画で流れる定番曲。“知っている”という安心感で自然と指やアンブシュアの練習に集中できます。
1オクターブ内で収まる曲
初心者は指回しと息のバランスが難しいため、無理な高音・低音に飛ばない曲から始めるのがおすすめです。
テンポがゆったり・単純なリズム
♩=60~80程度、四分音符が中心の楽曲から始めると落ち着いて演奏できます。“簡単に聞こえるけど奥が深い”曲が理想です。
例えば「アメイジング・グレイス」はこの条件を満たす代表格です。
筆者がクラリネットを始めた頃、 早く上手くなりたくて、張り切って難しいクラシック曲に挑戦したことで、予想以上に運指やブレスでつまづき心が折れかけました。
そんな時、楽器店の店員さんにおすすめされたのが「アメイジング・グレイス」。 子供のころから好きな曲で、自然に頭に旋律が浮かび、構成もシンプルなため「1音1音に集中する喜び」を味わえました。 「曲のハードルを下げることが長続きのコツ」だと実感した体験でした。
初心者向けおすすめ練習曲とその理由
アメイジング・グレイス
特徴:「Largo~Adagio」(♩=40~63)の穏やかなテンポ、同じフレーズの反復が多く、一息ごとに「丁寧な音作り」を意識できます。
練習メリット:ロングトーン+クレッシェンド/デクレッシェンド(強弱変化)の基礎練として有効。ブレスポイント(息継ぎ位置)の練習にも最適です。
練習ポイント:「Amazing Grace=素晴らしき神の恵み」という意味を持つ賛美歌で、敬虔で穏やかな雰囲気を意識すると表現力が育ちます。「静けさ」「感謝」「癒し」というイメージを持ちましょう。
最初はなかなかスムーズにメロディを吹くことができず、途切れてしまうことに落ち込みましたが、「フレーズごとに区切って録音→聞き返し→運指の修正」を繰り返すことで、少しずつ滑らかにつなげられるようになりました。
讃美歌ですので、「静けさ」「感謝」「癒し」といったイメージを持つことも効果的でした。録音することで「今日は音が柔らかくなった!」という成長が客観的に分かり、練習が楽しくなりました。
歓喜の歌(ベートーヴェン)
特徴:ゆったりとした中音域メインの旋律。運指やタンギングの基礎練習に効果的。
独自テク:「まずスラーで吹く→慣れてきたらタンギングを入れる→強弱のメリハリ」と段階を分けて練習すると、初心者でも無理なく表現の幅が広がります。
体験談:
練習ポイント:歓喜の歌は「喜び」を表現する曲なので、明るく、前向きな音色を目指すと◎。吹く時の気持ちは「嬉しい」「喜び」を人に伝える、または「お祝いする」といった気落ちを感じると音が明るくなります。
テンポはModerato(♩=76~96)がおすすめ
シンプルで分かりやすいメロディで、タンキングの上達につながる曲でした。
「テンポ60で正確に」を毎日確認し演奏したことで、指が自然に動くようになりました。最初はタンギングせず、全てスラーで吹いてみることを先輩に勧められ、継続したところ、タンギングに苦手意識がなくなりました。
見上げてごらん夜の星を(坂本九)
特徴:ゆったりとしたメロディでクラリネット特有の温かい音色を引き立てます。曲の中で同じフレーズが何度も登場するので、運指の定着に効果的。一度覚えれば、繰り返し練習することで表現の幅を広げることができます
練習メリット:高音や低音の跳躍が少なく、アンブシュアの安定や音色のコントロールの力が身につきます。メロディの表現力を養うにもおすすめです。
歌詞の世界観「夜空」「星」「静けさ」「希望」をイメージ。フレーズ毎に、メロディのニュアンスを変えてみましょう。演奏に深みがでます。テンポはAdagio〜Andante(♩=56〜76)がおすすめ
日本人には、馴染みの強い一曲。この曲では「息使い」に重点を置いて練習しました。息を深く吸って楽器全体を響かせる感覚が身につき、自分でも驚くほど豊かな音色を出せるようになりました。
ただ、メロディに表現をつけることが難しく悩んでいたところ先輩から、「1音目の響きを丁寧に出すことを意識してみて、メリハリをつけてみて」とアドバイスをもらいました。
冒頭の音が安定すると、曲全体がぐっと聴き映えするようになったと感じました。
虹の彼方に(映画『オズの魔法使い』より)
特徴:メロディは中音域が中心で、無理のない運指で演奏ができます。低音から高音に移る運指の練習にもなり、また息のスピードやアンブシュアの基礎力を高めることができます。
練習メリット:曲全体が穏やかで、ロングトーンを安定される練習に最適。またオクターブ跳躍で、運指の練習に、高音域を出すことに慣れることができます。
練習ポイント:歌心が求められる曲で、フレーズの始まりと終わりのニュアンスを丁寧に吹き切れるよう、意識しましょう。クラリネットで「歌う」感覚を養うのにぴったりの教材です。
憧れの先輩が、よく個人練習で吹いていて、真似して吹くようになったのですが、最初は高音が裏返ってしまい、安定させること、綺麗な音を出すことに苦戦しました。
何度も繰り返すことで徐々に、息のスピードのコントロールと、アンブシュアのコツがつかめてきて、安定した響きを得られるようになりました。
初心者が陥りやすい失敗とその対策
失敗例1:難易度の高い曲から始めてしまう
ついつい、「演奏してみたい曲」「憧れの曲」に挑戦してしまいがちですが、テンポが速かったり、音符があちこちにうごくような曲は、初心者には難しいハードルが高く、挫折しやすくなってしまいます。
初心者の頃、母親の好きだった「アルルの女」を早く吹きたくてチャレンジ。まったく指使いが曲のスピードについていけず、かえって自信をなくすことに。憧れの曲は先の目標として、今回おすすめしたような挑戦しやすい曲からチャレンジしましょう。
対策:簡単なメロディーから始めて徐々にステップアップすることで、成功体験を積み重ねられます。「成功体験」がモチベーション維持には大切です。最初は音域が狭く、テンポがゆっくりした曲を選ぶことが重要です。
失敗例2:音色よりも音量を重視してしまう
初心者は「大きな音を出すこと」に集中しがちですが、これでは息使いや音色のコントロールが疎かになります。ただ「音を鳴らす」ことを意識してしまうと、表現力も身につけることができません。
筆者は、初めたばかりの頃、先輩の音量に追いつこうと、とにかく「鳴らす」ことを追いかけてしまい、そのことでかえって周りの音色から浮いてしまった経験があります。
対策:音量も大切ですが、息のスピードやアンブシュアのコツをつかみ、「響きのある音色」を意識して練習することが大切です。息を深く吸い、メロディに合わせた息使いを身につけることで、クラリネット特有の柔らかい音色を引き出せます。
失敗例3:練習曲を頻繁に変えてしまう
一つの曲を十分に練習せずに次々と新しい曲に手を出すと、高められるはずの技術が、定着させることもできなくなります。
対策:一つの曲をしっかり仕上げることで、基礎技術が身につきます。特に初心者時代は「この曲なら完璧に演奏できる!」という自信を持てるようになるまで練習することが重要です。
初心者が練習曲を楽しむためのコツ
曲の背景や意味を調べる
練習する曲の背景や歌詞(歌詞付きの場合)を調べることで、その曲への理解が深まり、演奏に感情を込めやすくなります。例えば、「アメイジング・グレイス」は宗教的な意味合いが強い曲ですが、その旋律には癒しと希望のメッセージが込められています。
小さな目標を設定する
初心者時代には「今日はこのフレーズを完璧にする」など、日の目標、1週間の目標、など小さな目標を設定すると達成感が得られます。達成感はモチベーション維持に大きく役立ちます。
自分の演奏を録音して聴く
自分の演奏を録音して聴くことで、改善点や上達した部分を客観的に確認できます。
筆者も初心者時代には毎週録音して、聴いていました。自分がイメージしている感じと、録音した音では、最初は辿々しいメロディで落ち込むこともありましたが、反面、自分の成長を感じることもできました。成長を感じられることと、何を修正すればいいかが明確できるこが、モチベーションを高めることにつながりました。
まとめ
始めの一歩は「できるだけやさしい曲」を指標に、自分の好みにあわせて選ぶのが長く続ける最大のコツです。筆者自身も、「少しずつ成長を記録し、自分を褒める」ことでモチベーションを維持しています。
お気に入りの曲が増えれば人前で披露したくなり、さらに上達が実感できるでしょう。焦らず、練習していきましょう。

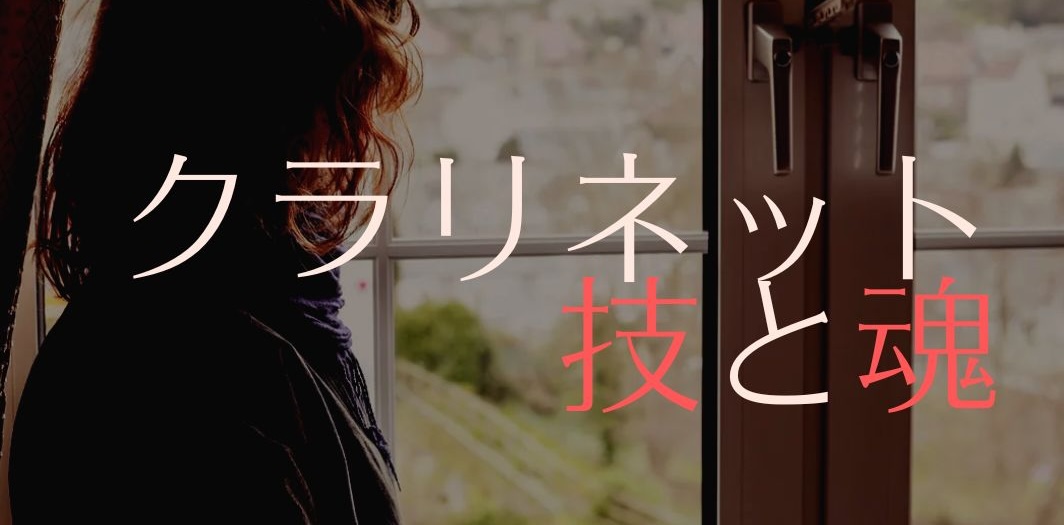
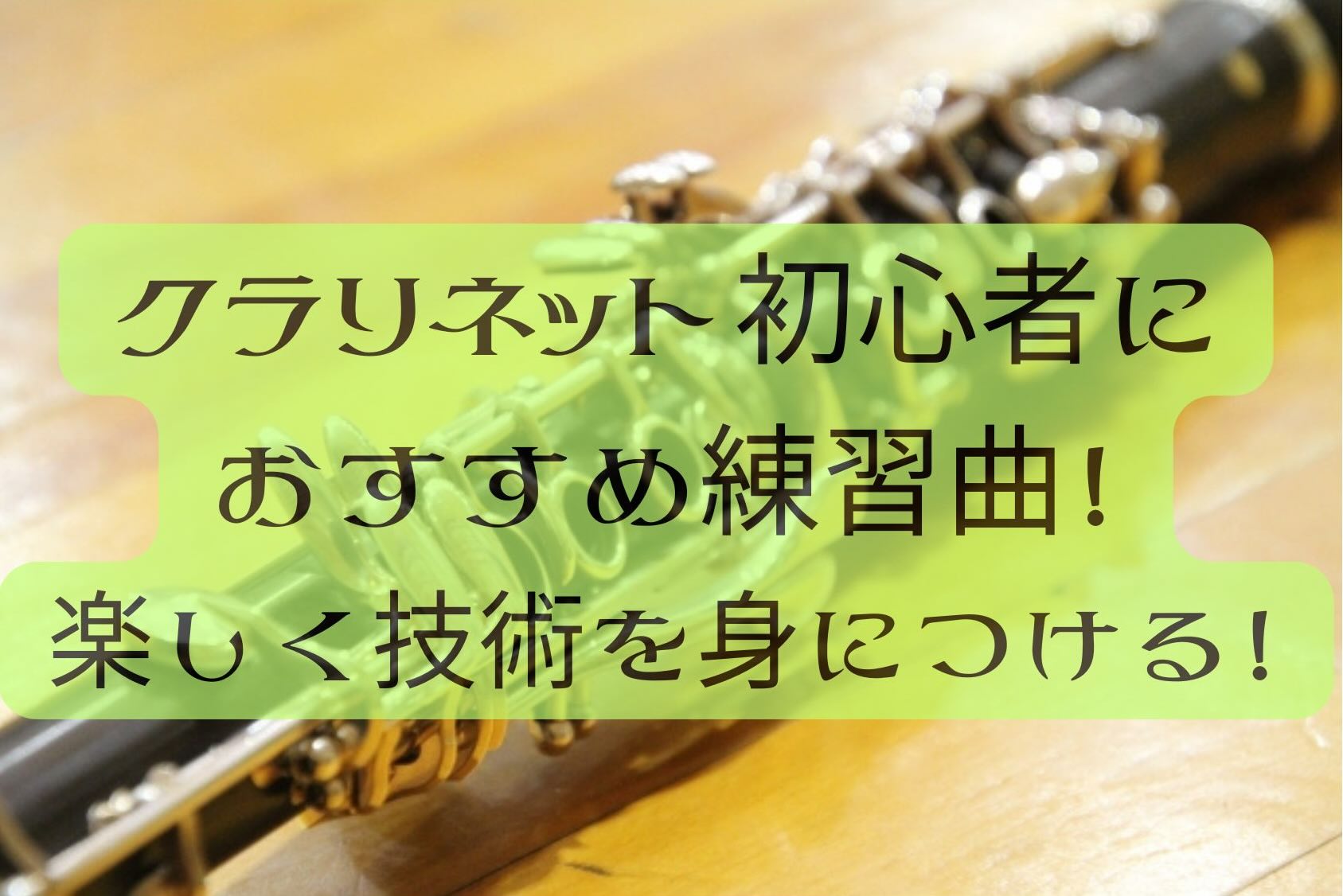
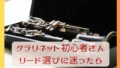

コメント