楽器を始めて間もない頃、私は「どうしてこんなに音が出にくいの?」「指が全然回らない…」と、壁にぶつかってばかりでした。
多くの初心者が同じように悩みを抱えると思います。音が鳴らない、響かない、体力がもたない…。そのたびに「自分は向いていないのかもしれない」と落ち込んだことさえあります。ですが、少しずつ工夫を積み重ねることで、演奏は必ず変化していきました。
本記事では、私自身が経験した失敗談や、そこから得た改善のステップを交えながら、初心者がつまずきやすい問題について深掘りしていきます。
初心者が陥りやすい悩みとその原因
音が響かない、ならない
原因:
- アンブシュア(口の形・噛み方)の問題
- 息の入れ方、支えの不足
- リードが古い、割れている
- マウスピースとリガチャがずれいてる、リガチャが曲がっている。
- 楽器の扱いに慣れていない
- メンタル的な焦りで体が力んでしまう
解決法:
- 下唇を歯に軽くのせ、リードを支えるバランスを覚える。
- 「噛む」のではなく「包む」イメージで口を作る。
- 毎日腹式呼吸を練習し、息をまっすぐ、スピードを意識して送り込む。
- リードを交換する。マウスピースとリガチャを変える。
- しっかりとキーを押さえ、ホールを塞いでいるか鏡で確認する。
- 力んで肩が上がらないように、口周りに力が入りすぎないようチェックする。
「先輩のように、全然音がならない、響かない…」と悩んでいた頃の私は、楽器のどこかが調子が悪いのではと思ったほどでした。先生に相談すると、問題は楽器ではなく、私の息の使い方にあると判明。
私は腹式呼吸をしているつもりが、吹いている途中から胸式の呼吸に戻ってしまっていて、そのせいで、楽器にしっかりと息が吹き込めていませんでした。
先生に、腹式呼吸の練習を勧められ、毎晩寝る前に横になり、4拍吸って8拍吐く練習を続けたところ、1か月後には低音が以前よりも温かく響くようになりました。
さらに、リードの選び方についても、先輩からアドバイスをいただき、吹いた時に自分が吹きやすいリード、吹きにくいリードの違いもわかるようになったことで、音色が大きく改善。楽器演奏には、自分の体の使い方が大切だと痛感できた経験でした。
タンギングが遅れる、うまく当たらない
原因:
- 舌の動きが大きすぎる。
- 息の流れが止まっている。
- 舌の位置が適切でない。
解決法:
- 息の流れを安定させるためにロングトーン練習を行う。
- ロングトーンをしながら、リードに舌を軽く当てる練習をする。
- 舌先をリードにそっと触れる程度にする。
舌で「トゥッ」と発音する感覚をつかむのに私は相当苦労しました。最初は舌をべったり押し当ててしまい、息の流れが止まってブツブツ切れた音になっていたのです。先生に「力を抜いて、舌先だけを軽く触れるイメージ」と言われても、頭ではわかっても身体はなかなか思うように動いてくれませんでした。
そこで私は、声を実際に出しながら「トゥートゥートゥー」と声に出し、それをそのまま楽器で再現する方法を取り入れました。毎日続けるうちに、ある日突然「これだ!」という感覚を得られ、タンギングが自然につながるようになりました。
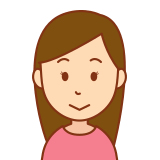
「トゥートゥートゥー」ですよ!
指がもつれる、速いフレーズで乱れる
原因:
- 指に余計な力が入っている。
- 指と息のタイミングが合っていない。
- 基礎練習不足による技術不足。
解決法:
- メトロノームを使ってゆっくり正確に指を動かす練習をする。
- 指に力を入れず滑らかに動かすことを意識する。
- 基礎練習(音階練習やクロマチック練習)を毎日行う。
私は、ピアノ経験者だったので、未経験の人よりは指が動く方ではありましたが、クラリネットは、指使いで音が途切れやすいところがあり、音が転ぶことが多くありました。特に初心者のころは、テンポが速い曲の連符では指が追いつかず、合奏時に脱落…。
そんな私の転機は「一番遅いテンポ」から始める練習を徹底したことです。当初はテンポ40で16分音符を吹くという地味な訓練でしたが、音と指を「完全に一致させる」ことに集中しました。徐々にテンポを上げていくと、ある日「指が先に動いている感覚」から「音と一体化する快感」に変化しました。
この経験を通じて、速さよりも「正確性こそが土台」だったことを実感しました。
初心者向け!ミス克服のための実践的アドバイス
鏡を使ったセルフチェック
ポイント:鏡を使って自分の姿勢やアンブシュア(口の形)、マウスピースを咥える深さ、曲がっていないかなど確認をしましょう。客観的に自分の演奏フォームを見直すことができます。
特に初心者は、自分では正しいと思っていても実際には力が入りすぎていたり、それが原因で曲がって咥えてしまっていることがあります。鏡を活用することで、これらのミスを早期に修正できます。早めに修正しないと、変な癖がついてしまいます。
私が初心者時代に効果を実感したこと、また印象に残っているのは、「吹いている自分を鏡で見る」練習です。吹いている自分を見返すと、知らず知らずに口元が曲がっていたり、マウスピースの咥え方が浅かったりと予想外の癖に気づけます。
また、長時間の練習では姿勢が崩れてしまいがちなので、鏡を前にして「肩が上がっていないか」をチェックする癖をつけました。さらに、メトロノーム練習は「リズムを合わせる道具」ではなく「自分の呼吸を整える相棒」だと考えるようになってから、練習の質が飛躍的に上がりました。
そして最も大切なのはロングトーン。今でも私は毎日5分でもいいから息を一定に保つ練習を欠かしません。これが自分の調子や、楽器の調子、そしてリードの良し悪しまで確認できる時間になっています。
メトロノームを使った練習
ポイント:メトロノームを使うことで、正確なリズムで練習ができます。ロングトーン、タンキング、音階練習などなど、メトロノームは欠かせない存在です。
早い指回しを練習したい時は、最初はゆっくりとしたテンポで練習し、慣れてきたら徐々にテンポを上げていく方法がおすすめです。焦らず一歩ずつ進めることが大切です。
早いパッセージ(速いフレーズ)を練習するとき、最初は指が追いつかず音がぐちゃぐちゃ。でもメトロノームを40くらいの遅いテンポにして、ゆっくり正確に吹く練習を繰り返しました。
それを50、60…と少しずつ速くしていくと、あるとき、「あ、指がついてくる!」という感覚を得られました。焦って速く練習していたときには絶対に身につかなかった感覚でした。
ロングトーン練習で息使いを改善
ポイント:ロングトーン(1つの音を長く伸ばす練習)は、息の流れや音色の安定性を向上させるために非常に効果的です。特にこの練習は毎日のルーティンに取り入れるべきです。
音量や音色が一定になるよう意識しながら、低音から高音まで幅広い音域で行うとさらに効果的です。
筆者は基礎練習で、まずはロングトーン練習から始めます。これは、中学生のころから欠かせません。初心者のころから、1日10分間続けた結果、安定した音色が出せるようになりました。腹式呼吸が自然と身につく練習でもあります。
実は、高校生の頃、ロングトーン練習をさぼったことがあります。すると、2、3週間で音色が変わってしまい、先生に「下手になったね」と言われてしまったことも。
2度とさぼるまい!と、それからは、欠かしたことがありません。時間がない時も、ロングトーンだけは、必ず行います。今では、自分の調子、リードの調子、楽器の調子を確認できる時間にもなっています。
よくある悩み別!具体的な解決法
悩み1:高音域で音が割れる
原因:
- 息のスピードが足りない。
- アンブシュアが不安定。
- リードやマウスピースが適切でない。
解決法:
- 息を速く吹き込むことを意識する。
- アンブシュア(口周り)を均等に保つ練習を行う。
- 高音域用に適したリードやマウスピースを選ぶ。
悩み2:長時間演奏すると疲れる、体力・息が続かない
原因:
- 姿勢が悪く、口周りに余計な力が入っている。
- 腹式呼吸がいつの間にか胸式呼吸になっている。
解決法:
- 正しい姿勢(背筋を伸ばし肩はリラックス)で演奏する。
- 腹式呼吸を意識し、深い息で吹く練習を行う。
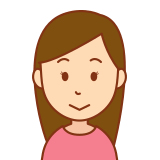
腹式呼吸は、とにかく慣れること!毎晩寝る前や、朝起きた時に、横になったまま腹式呼吸の練習をしましょう!
特に苦労したのは高音域でした。初めのころは音がかすれたり、ギャーっと金属的な音が出て悔しい思いをしたこともあります。
先輩にアドバイスをいただき、「息のスピードを速くする」「口周りを均等に保つ」ことを徹底。リードの硬さも調整した結果、音が安定しはじめました。 また、体力面では最初の30分でバテてしまい、合奏練習についていけませんでした。
寝る前に横になって腹式呼吸の訓練をする習慣の継続で、1時間以上吹いても息が切れなくなり、演奏そのものを楽しめるようになったのです。
まとめ
初心者が感じる「音が出ない」「息が続かない」「指が遅れる」といった悩みは、誰もが通る道です。私自身、何度も「もうやめようかな」と思いましたが、小さな工夫と継続で必ず改善されます。
自分だけができないのではありません。同じ悩みを乗り越えた先には、演奏の楽しさが何倍にも広がっていることを、私は経験を通して確信しています。
特に、腹式呼吸や、指練習は、継続が大切です。すぐには結果がでませんが、継続により、ある日「あ!変わった」を感じる瞬間が必ずあります。楽しみに頑張っていきましょう!

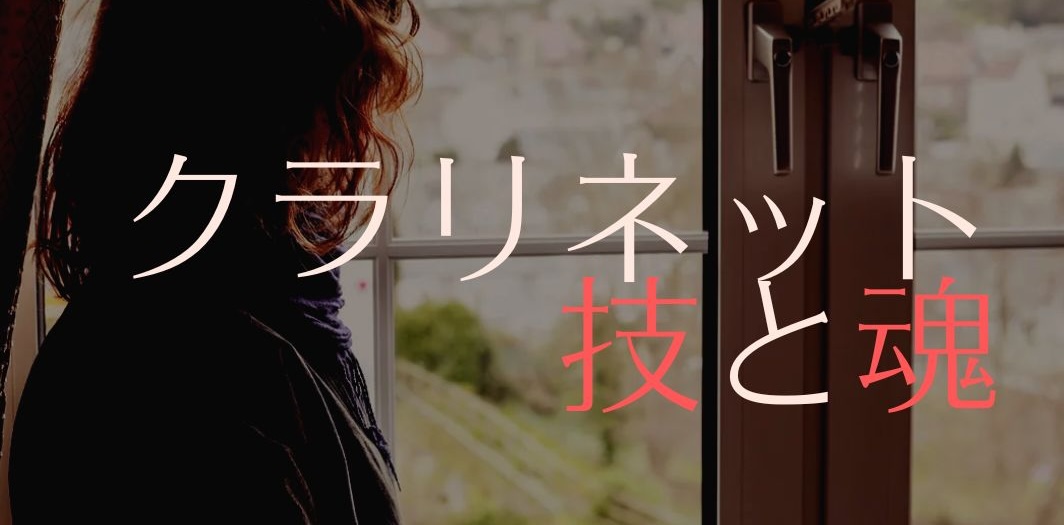
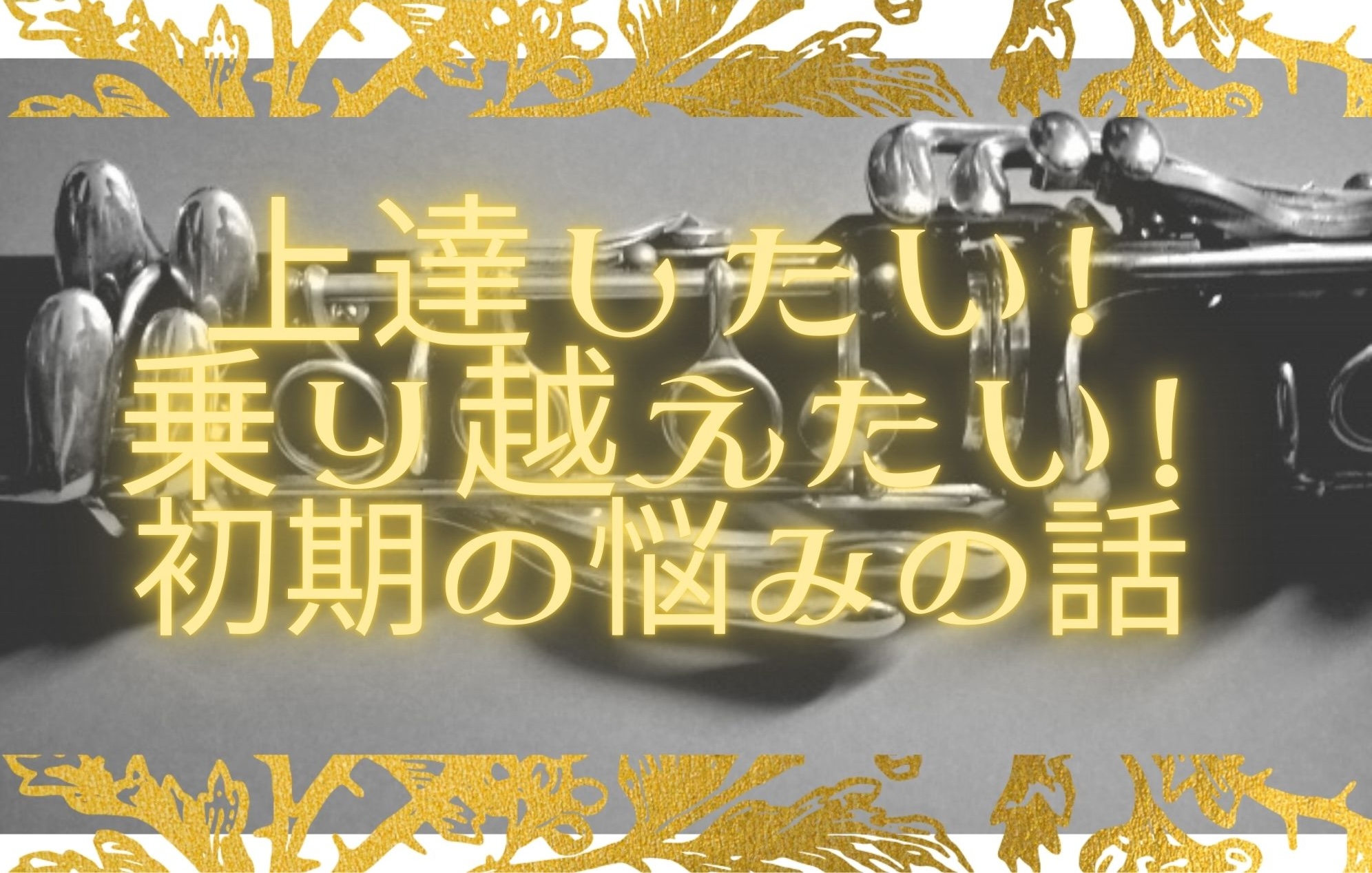
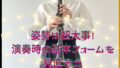

コメント