クラリネットと言えば、クラシック音楽の優雅な響きやオーケストラでの繊細な役割を思い浮かべる人が多いでしょう。
クラリネットは、クラシックだけではなく、ポップスやジャズの世界でも実は活躍をしています。
ジャズの世界に入ると、まるで違う表情を見せます。軽やかに跳ねるスウィング、時には力強く、時には甘く囁くような音色…。
この記事では、クラシックとジャズにおけるクラリネットの表現の違いを、演奏者の体験談や筆者自身の経験を交えて掘り下げます。
クラリネットの音色と奏法の違い
クラシックで求められるクラリネットの音色
クラシック音楽のクラリネットは、まるで絹のように滑らかな音色が理想とされます。オーケストラや室内楽では、他の楽器と溶け合うような深みのある響きと安定した音程が求められ、演奏者は一音一音に細心の注意を払います。
私も大学生時代、管弦楽の一員として演奏した際、指揮者から「音を際立たせず、管弦楽の色に自然に溶け込むように」という指示を受けたことが、印象に残っています。
ジャズでのクラリネットの特徴的な奏法
ジャズの舞台に立ったクラリネットは、クラシックで求められる整った音色とは一変します。柔らかい音だけでなく、少し荒さを含んだ音、そして観客の空気を直感で捉えた瞬間の一音が輝きます。
私が初めてライブハウスでジャズクラリネットを聴いたとき、楽譜の枠から解き放たれた自由さと、演奏中に観客が体を揺らす姿を見て「この音楽は生きている」と感動を覚えました。
クラリネット奏者でありジャズプレイヤーとしても活動している先輩、山中さん(仮名)にお話を伺いました。
山中さん(仮名)は長年クラシックの吹奏楽団で活躍していましたが、ある日訪れた小さなジャズバーで聴いたクラリネットの音が、まるで楽しそうに会話をしているように感じたそうです。
その瞬間、「この自由さを自分も表現したい」と感じたそうです。転向直後は楽譜なしで演奏することに大きな不安を覚えたものの、毎週のセッションでリズム感と音楽理論を少しずつ身につけ、自分だけのジャズスタイルを築いていきました。
ジャズの即興演奏では、クラシックとは異なる柔軟性が求められます。山中さんは「ジャズの世界では、楽譜に頼らずその場の雰囲気に合わせた演奏をしなければならないので、最初は難しかったです。
でも、観客との一体感を感じた時の喜びは何にも代えがたいです」と話してくれました。
ジャズクラリネットの代表的な楽曲と影響
ベニー・グッドマンの功績
ジャズクラリネットの象徴的存在であるベニー・グッドマンは、クラリネットをジャズの中心楽器として広めました。彼の演奏スタイルはクラシックの技術を取り入れながら、ジャズの自由な表現を追求したものです。
ぜひ、「ベニーグットマン物語」という映画を鑑賞してください!かっこよさに痺れますよ。
ジャズクラリネットの魅力を引き出す楽曲
ベニー・グッドマンの「Sing, Sing, Sing」は、クラリネットがジャズの中心にあることを世界に示した名曲です。冒頭のドラムが鳴り響く瞬間から、観客は大きな波に巻き込まれるような高揚感を覚えます。
私も初めてこの曲を吹いたとき、緊張で指が震えましたが、終盤に観客が拍手と共に立ち上がった瞬間、その感動は忘れられないものとなりました。
もうひとつのおすすめは「Memories of You」。これはまるでクラリネットが語りかけるような優しいメロディで、夜の静けさにそっと溶けていくような魅力があります。
高校時代の演奏会で、先生に勧められて挑戦した、筆者にとっては思い出深い1曲です。
ジャズクラリネットの吹き方のコツ
ここからは、実際にジャズクラリネットを演奏するうえで大切なポイントやコツについてご紹介していきます。演奏をより自由に、そしてジャズらしい響きに近づけるためのヒントにしてください!
音色(トーン)を変える意識を持つ
ジャズクラリネットでは、自分だけの音色が最大の武器です。クラシックのように完璧に整える必要はなく、わずかな癖や深みが演奏に温かさと説得力を与えます。
例えば、アンブシュアを少し緩めてリードに自由な振動を与えると、ざらついた味のある音になります。また、グロウルやサブトーンなどの特殊奏法を取り入れることで、観客の耳を惹きつける個性的な演奏が可能です。
クラシックのように「キレイに整えすぎない」ことが、ジャズの味になります。
スウィング感を身につける
-
ジャズではリズムが命!特に「スウィング」は最重要。
-
8分音符は「タタタタ」ではなく「タ〜タ タ〜タ(3連符のように)」と後ろを跳ねるイメージで。
Tip:録音(ベニー・グッドマン、アート・ペッパーなど)に合わせて耳でリズムを覚えると効果的!
アドリブ(即興)に慣れる
-
最初は難しく感じるけど、スケールやリック(定番フレーズ)を覚えておくと楽になります。
-
よく使われるスケール:
-
ブルーススケール
-
ドリアンモード
-
ミクソリディアンモード など
-
「1フレーズ=呼吸1回」で作っていくと自然なアドリブになります。
音符の長さに“言葉”のリズムを入れる
-
ジャズは「言葉」のような音楽。しゃべってる感覚でフレーズを作るとグッとジャズっぽくなります。
-
スタッカートやアクセントを、メロディの中で「意味をもたせて」使うのがポイント。
クラリネットならではの表現も活かそう!
-
ジャズでもクラリネット独特のグリッサンド(音を滑らせる)やベンド(音程をわずかに上げ下げ)など、柔らかい表現が活きてきます。
-
クラリネット特有の「音の立ち上がりの柔らかさ」は、ジャズで特に武器になります。
特殊奏法
通常のクラシック演奏ではあまり使わないテクニックがいくつもあります。現代音楽、ジャズ、前衛的なソロや即興演奏などでよく使われます。
ジャズ向きの奏法をいくつかご紹介します。
【音色・音の出し方を変える系】
① フラッタータンギング(flutter tonguing)
-
舌を巻いて「ブルルルル」と震わせながら吹く。
-
効果:ざらついた音、怪しげな雰囲気。現代音楽や映画音楽などで多用。
-
コツ:舌を巻くのが難しければ「喉のフラッター」でもOK
- 例:サイレン音、魔法っぽい効果音
② グロウル(growl)
-
声を出しながら同時にクラリネットを吹く。
-
効果:ジャズなどで「うなり声のようなサウンド」が出せる。
-
コツ:喉をリラックスさせて、クラリネットを吹きながら低く唸るように。
- ベニー・グットマンやスムースジャズ風サックスでも使われる
【音程・音高を変える系】
① グリッサンド(glissando)
-
音を連続的に滑らかにつなげる(例:ド〜シまで“滑らかに”上がる)。
-
効果:幻想的な印象、またはコミカルにも使える。
-
コツ:
-
指の滑らかな動き(指を少しずつ浮かせる)
-
同時に口元で音程を操
-
例)ガーシュウィン『ラプソディ・イン・ブルー』冒頭のクラリネット
-
② フラジオレット(ハーモニクス/倍音奏法)
-
特定の運指+息のスピードを調整して、高次倍音を発音する。
-
効果:通常より高く、鋭い音色。高音域の拡張や特殊効果に。
-
コツ:「基音」となる指使い+アンブシュア・息の角度が重要。
練習のポイント
最初は、楽譜に書かれているsoloのメロディを、そのまま吹いて慣れることをおすすめします。慣れてきたら、それをアレンジしていきましょう。
録音して、自分で聴いてみるのが上達の鍵です。
まとめ:クラリネットの可能性を広げよう
クラリネットは、クラシックでは精緻で優雅な響きを奏で、ジャズでは自由と情熱を全開にして語りかける楽器です。
演奏者自身の人生経験や感情が音色に直接反映されるのがジャズの醍醐味。
もしあなたが新たな音楽の世界を探しているなら、ジャズクラリネットは挑戦しがいのある最高のフィールドになるでしょう。

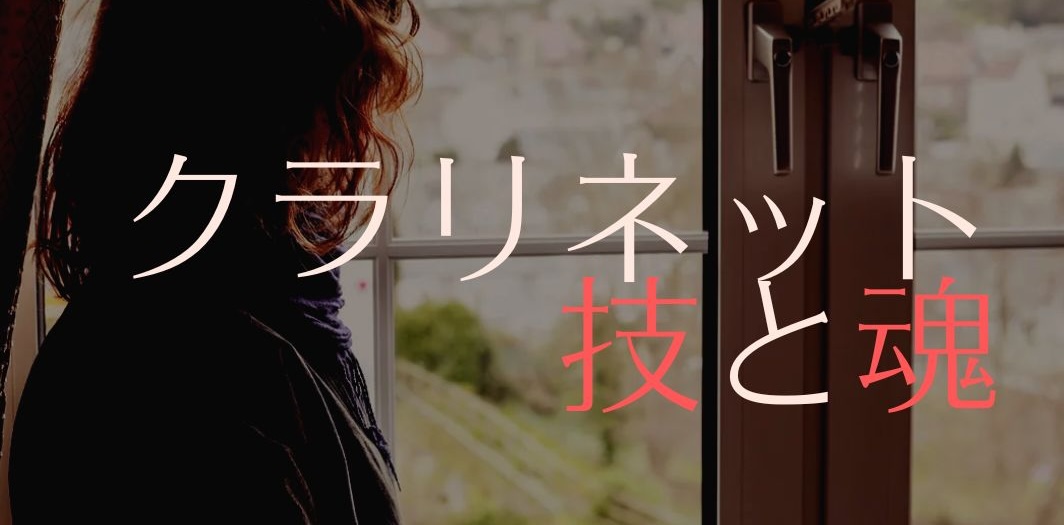
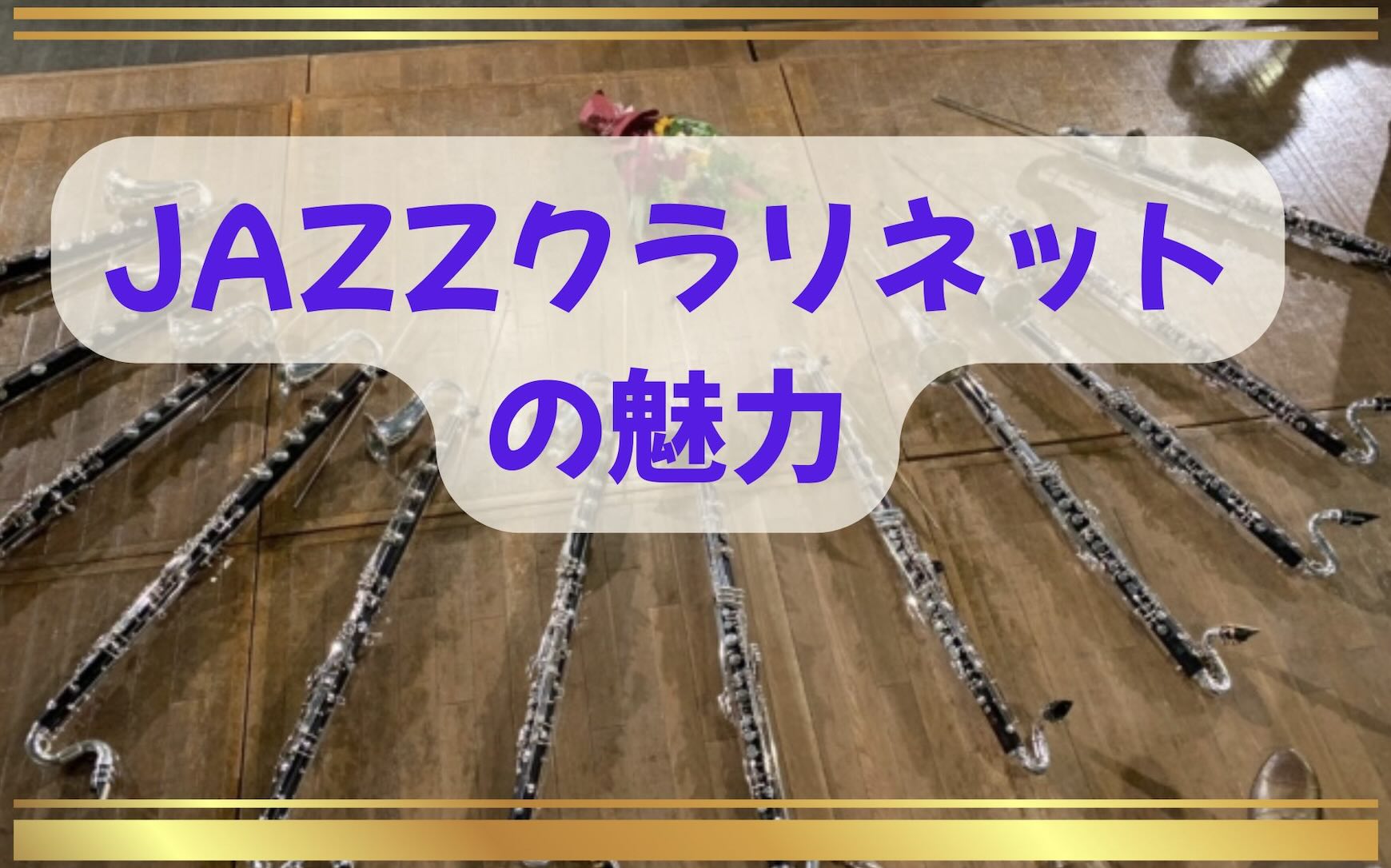
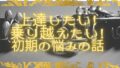
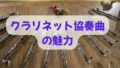
コメント