私にとってクラリネットは、柔らかな音色に一瞬で心を奪われた楽器です。
一般の方には、「あのリコーダーみたいなやつ?」って言われませんか?フルートやサックス、トランペットと比較すると地味な見た目、と言えるかもしれません。
しかし、実は木管楽器の中でも特に表現の幅が広く、吹奏楽やオーケストラはもちろん、ジャズや映画音楽でも活躍の幅も広い楽器の一つです。
実際に演奏してみると、その音色の奥深さや、息遣いによって変わる表現力の豊かさに驚かされます。
クラリネットがどのように発展してきたのか、そしてその魅力とは何なのかを知る人は少ないかもしれません。本記事では、クラリネットの基本情報や歴史、種類、そして実際の演奏者が語る体験談を交えながら、その奥深い魅力を徹底解説します。
クラリネットの歴史と進化
クラリネットの起源は「チャルメラ」
クラリネットの起源をたどると、ヨーロッパに伝わった「シャリュモー(チャルメラ)」という素朴な木管楽器に行き着きます。
実際、私が楽器博物館でシャリュモーを見たとき、その素朴な形や温かい音色が、現代のクラリネットに通じていると感じました。この歴史の流れを知ることで、クラリネットの音色に込められた奥深さをより身近に感じられるようになりました。

この歴史の流れを知ることで、クラリネットの音色に込められた奥深さをより身近に感じられるようになりました。
名前の由来は「小さなトランペット」
クラリネットという名前は、イタリア語の 「クラリーノ(clarino)」=高音のトランペット に由来します。
初期のクラリネットは金管楽器のように明るい音を出していたため、
「小さいトランペット(クラリーノ+エット → クラリネット)」と呼ばれるようになったそうです。
現代クラリネットの誕生
18世紀初頭、ドイツのヨハン・クリストフ・デンナーによって改良が施され、現在のクラリネットに近い形が誕生しました。
彼が追加した「レジスターキー」によって、楽器の音域が大幅に広がり、クラリネット独自の豊かな響きが生まれました。
演奏者が語る!クラリネットの魅力と挑戦
クラリネット経験10年以上の演奏者、田中陽子さん(仮名)にお話を伺いました。
クラリネットを始めるきっかけ
私がクラリネットを始めたのは中学の吹奏楽部でした。最初は「リコーダーみたいな楽器?」という軽い気持ちで手に取ったのですが、初めて音を出した瞬間、予想以上にまろやかで温かい響きに驚きました。
特に、部活の先輩が奏でる低音の深さと高音の華やかさに驚き、憧れ、「自分もこんな音を出したい」と思ったことが、今も続けている原動力です。
練習では、指使いの難しさや、思い通りに音が出ないもどかしさに何度も挫折しかけました。でも、ある日突然、苦手だったフレーズがすっと吹けるようになった瞬間の達成感。今でもその感覚が忘れられません。
練習の壁と乗り越えた瞬間
「指使いが複雑なので、最初は本当に苦労しました。でもある日、練習でどうしても弾けなかったフレーズが突然吹けるようになり、達成感と自信が湧きました」と話してくれました。
日々の努力が結果に結びついた瞬間の感動は、何物にも代えがたいものです。楽器経験者は誰もが共感するところだと思います。

クラリネットの種類とその特徴
クラリネットには実はたくさんの種類があり、それぞれ音の高さ・大きさ・用途が違います。ここでは、代表的なクラリネットの種類を、音の高さ順に分かりやすく紹介しますね
E♭クラリネット
華やかで鋭い高音が特徴。主にスパイス的な役割を果たします。トゥッティ(全体合奏)の中でも音が抜けて響くので、アクセントとして効果的に使われます。不気味さ・滑稽さ・緊張感を演出するために使われることも多いです。
吹奏楽では、高音メロディの強化役/補強役として活躍。トランペットやフルートとユニゾンまたはオクターブ上でメロディを奏でることも。
- 調性:E♭(変ホ調)
- 特徴:ソプラノクラリネットより短く、高音が鋭くて華やか
- 用途:吹奏楽、オーケストラ(近代〜現代作品)、たまにジャズ
- 難しさ:音程が不安定になりやすいので、上級者向き
🎵 有名曲:ショスタコーヴィチ《祝典序曲》、ベルリオーズ《幻想交響曲》
学生バンドでは、持ち替えで演奏される姿もよく見かけます。筆者も、持ち替え経験者です。
私が初めてE♭クラリネットを吹いたのは高校の吹奏楽コンクールでした。B♭クラリネットよりも小さく、手に持ったときの軽さに驚きました。
さらに、実際に演奏してみると、高音がキラキラと響き、全体合奏の中でも自分の音が突き抜けてしっかりと聴こえてくるのが印象的でした。これは、他のクラリネットとは違う感覚です。
特に、行進曲のクライマックスでE♭クラリネットが加わると、音楽全体が一気に華やかになるのを実感しました。
B♭クラリネット
最も一般的なクラリネットで、吹奏楽やオーケストラで頻繁に使用されます。初心者が最初に手に取る楽器としてもおすすめされています。
- 調性:B♭(変ロ調)
- 特徴:もっとも一般的で標準的なクラリネット
- 用途:クラシック、吹奏楽、ジャズ、ポップスなど全ジャンル
- 補足:中学生や初心者もまずこれから始めます!
🎵 モーツァルトの協奏曲や、ジャズクラリネットもこのタイプが主流
Aクラリネット
クラシック音楽でよく使用され、特にモーツァルトやブラームスの楽曲で活躍します。
- 調性:A(イ長調)
- 特徴:B♭クラリネットと非常に似ているがやや長く、柔らかい音
- 用途:クラシックのオーケストラ、特にモーツァルトやブラームス作品
- 補足:プロのオーケストラ奏者はB♭とAを持ち替えることが多い
🎵 モーツァルトのクラリネット五重奏曲、ブラームスのクラリネットソナタ
Cクラリネット
歴史的な楽器で、魅力的な音色。通常のB♭クラリネットより半音低い音域を持っていて、クラシック音楽の中で特に個性的な存在。
- 調性:C(ハ長調)
- 特徴:移調しない数少ないクラリネット(ピアノと同じ調性)
- 用途:透明感のある音色で、特に古典派やロマン派の音楽に適している。昔のオーケストラ作品や、古典派の室内楽などにまれに登場
- 補足:サイズも少しコンパクトだから持ちやすい。モーツァルトの「クラリネット協奏曲」ではCクラリネットがよく使われていた。
アルトクラリネット(E♭)
クラリネットの中でも独特な存在で、優雅で深みのある音色を持つ。
- 調性:E♭
- 特徴:中低音の温かみのある音。温かく、まろやかで落ち着いた音色。中低音域が豊かで、合奏に厚みを加える。中低音パート(内声)として、メロディと低音の間をつなぐ役割。特にハーモニーの厚みを出すのに貢献します。
- 用途:吹奏楽、クラリネットアンサンブル、まれにオーケストラや現代音楽作品でも使われる。
- 補足:形状はB♭クラリネットより一回り大きく、カーブした金属製のネックとベル(サックスのような形状)を持つ

アルトクラリネットは演奏人口が少なく、学校や楽団によっては常設されていないこともあります。楽器自体が高価で、入手やメンテナンスにやや手間がかかる傾向があります。
🎵 アルフレッド・リード《エル・カミーノ・レアル》、ホルスト《第一組曲》《第二組曲》
バスクラリネット
低音域を担当するクラリネット。クラシック音楽では、オーケストラや室内楽の低音部分を支える役割が多く、ジャズでは深い響きがソロやアンサンブルで活躍します。
- 調性:B♭(1オクターブ下)
- 特徴:低音域での豊かな響きと心地よい音質。他の楽器にはない温かみと重厚感がある。
- 用途:オーケストラ、吹奏楽、現代音楽、ジャズなど幅広い
- 補足:まっすぐなボディにベルが金属でカーブしているのが特徴
🎵 ドビュッシー《牧神の午後への前奏曲》、ラヴェル《ボレロ》、エリックドルフィ「G.W.」、映画「ロード・オブ・ザ・リング」

コントラアルトクラリネット(E♭)
バスクラリネットよりもさらに低音が豊かで、ソロでもアンサンブルでも輝ける楽器。大きなサイズからくるその迫力ある音色が魅力。
- 調性:E♭(バスクラよりさらに低い)
- 特徴:超低音!見た目はバリトンサックスに近い。楽器も大きい!
- 用途:吹奏楽(特に大編成)での低音の支え、現代音楽の実験的な作品、映画音楽での感情的な表現。
補足:演奏機会は少なめだが、存在感はバツグン
🎵モーツァルト、ベートーヴェンの室内楽曲「エル・カミーノ・レアル」

コントラバスクラリネット(B♭)
クラリネットの中で最も低い音域を持つ。
- 調性:B♭(コントラアルトよりさらに1音下)
- 特徴:クラリネット属で最も低い音域。深く響く音が特徴。
- 用途:アンサンブルに厚みを与え、低音のベースラインを支える。現代音楽ではインパクトを与え、大編成のオーケストラで実験的な場面で効果的な役割を果たす。
補足:他のクラリネットよりもはるかに長い管と大きなベル。
映画音楽や現代作品で活用が増えています。

クラリネットを始めたい人へのアドバイス
必要な道具と選び方
クラリネットを始めるには、楽器本体、リード、リガチャー、クリーニング用品が必要です。初心者用のセットは比較的安価で手に入りますが、一度楽器店で試奏をすることをおすすめします。
初めて自分のクラリネットを選んだ時、私は楽器店で何本も試奏しました。見た目や値段だけでなく、「自分の息でどんな音が鳴るか」を大切にしたかったからです。
店員さんにアドバイスをもらいながら、最終的に「これだ!」と思える一本に出会えたときの感動は忘れられません。実際に吹いてみて、手に馴染む感覚や、音の出しやすさを確かめることが、納得できる楽器選びのポイントだと実感しました。
「私が初めて楽器を選んだとき、何を基準にすればいいのかわからず困りました。でも店員さんに相談して、自分の理想とする音に近い楽器を選ぶことができました。試奏した感覚も大事ですが、経験者や経験豊かな店員さんなどの意見を聞きながら選ぶことがいいですよ!」と田中さんはアドバイスをくれました。
直接試奏し、自分に合った楽器を選ぶのが成功の秘訣です。
中古楽器購入のポイントはこちら
https://corekaracorekara.net/141.html
クラリネットが広げる音楽の可能性
クラリネットはクラシックだけでなく、ジャズやポップスなど幅広いジャンルで活躍します。他の楽器とは違う、独特な温かみ、豊かな響きは、どんなジャンルにも溶け込める不思議な力があります。
例えばジャズのスイングでエネルギッシュなリズムを生み出したり、クラシックの中で美しい旋律を紡いだり。映画音楽でも印象的なフレーズを任せられたりしています。
シンドラーのリスト、アメリ、ロード・オブ・ザ・リングなど、ぜひ聴いてみてください!
新しい音楽表現が生まれるたびに、クラリネットの音も進化していきます。
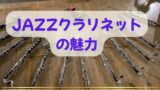
まとめ
クラリネットは、ただ楽譜通りに音を出すだけの楽器ではありません。吹く人の気持ちや個性がそのまま音色に現れる、不思議な魅力を持っています。私自身、クラリネットを通じてたくさんの音楽仲間と出会い、音楽の楽しさや奥深さを知ることができました。
これからクラリネットを始めたい方も、ぜひ自分だけの音色を見つけて、その世界を広げてみてください。
これを機に、クラリネットの音楽世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか?

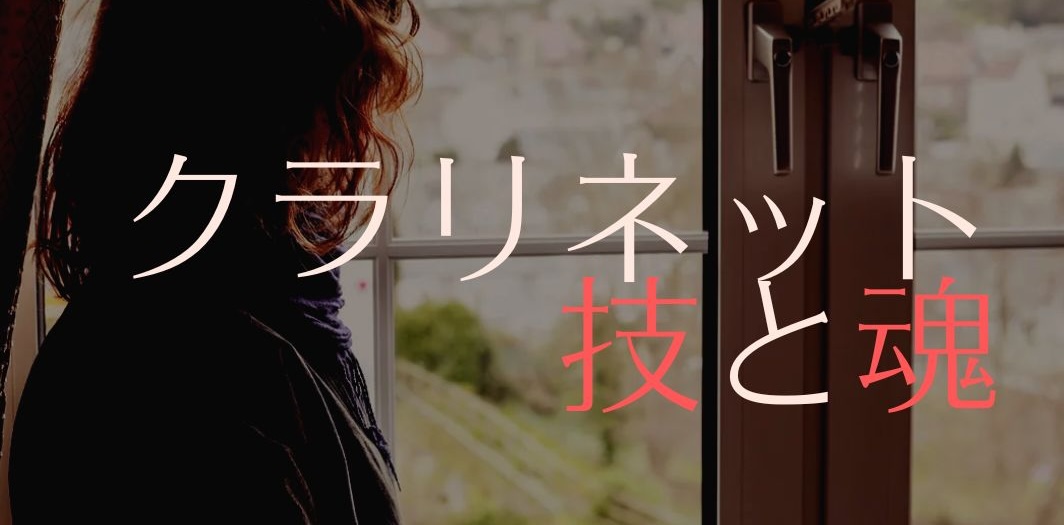
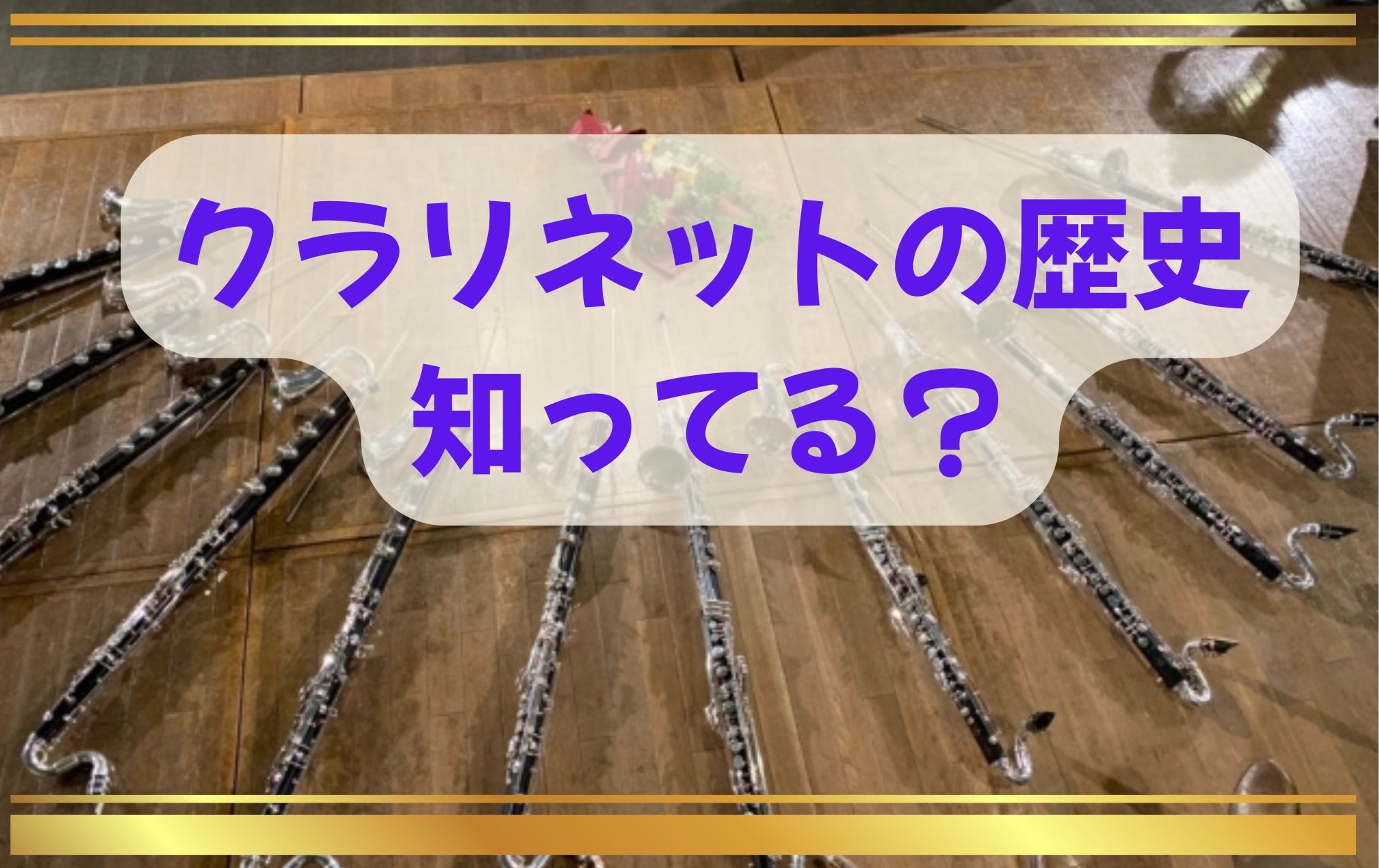
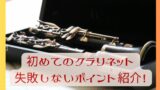
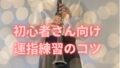
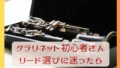
コメント