吹奏楽コンクールは、多くの学校や団体が参加する音楽の祭典です。演奏技術だけでなく、チームワークや計画的な準備が結果に大きく影響します。
日本では「全日本吹奏楽コンクール」が最大規模のものです。1940年に創設され、戦後の1956年に再開されました。中学生、高校生、大学生、職場・一般の部門に分かれており、各部門で審査が行われます。
中学生、高校生の部門は、演奏者の人数によりAとBに分けてプログラムが組まれています。
テレビ番組で「吹奏楽の旅」の中で、高校生たちが全国大会出場に向けて、練習に励む姿が何度も紹介されていますよね。筆者は、この番組を観ては、昔の自分たちと重ね合わせて感動をもらっています!
コンクールへの挑戦は、緊張と感動がたっぷりと味わえ、バンドのレベルを上げてくれる、一大イベントです。より良い体験と、結果を目指すためにも、コンクールに向けて準備をしていきましょう!
吹奏楽コンクール成功のための準備
全日本吹奏楽コンクール
各部門ごとに、県大会 → 支部大会 → 全国大会 と進みます。
大会毎に全出場団体に、金賞・銀賞・銅賞が与えられます。そして、金賞の中から、上位のコンクールに進む団体が選ばれます。
練習計画の立案
まず、コンクールに向けた練習計画を立てることが重要です。
演奏曲目(課題曲と自由曲)の演奏時間から、比重や点数の構成も考えた上で、練習時間を細かく分け、個人練習・パート練習、セクション練習(部分別に他楽器と一緒に合わせる)、そして全体合奏練習をバランスよく取り入れましょう。
特に合奏では、パート間のコミュニケーションを大切にすることで、音楽的な調和を高めることができます。さらに、日々の練習に課題を設けることで、効率的に進めることが可能です。
たとえば、「今日は音程の統一に集中する」「リズム感を強化する」など、パートリーダーさんは、具体的な目標を設定すると、全員の意思統一がしやすいです。
音楽性を深めるための取り組み
演奏技術だけでなく、曲の背景や作曲者の意図を理解することも重要です。自分たちで調べる、先生に話を聞くなど、曲の解釈を深めることで、演奏に豊かな表現力が加わります。
指揮者や指導者と意見を共有し、音楽的な方向性を明確にすることで、より魅力的な演奏が可能になります。
パート練習のポイント
吹奏楽の演奏の中で、各パートの仕上がりが全体の完成度に大きく影響します。パート練習では、以下の点に注意してください:
- 音程合わせ:同じパート内で音程を正確に合わせることで、全体の調和が向上します。
- リズムの統一:リズムのずれが全体の演奏を乱す要因となるため、細かい部分まで揃える練習が必要です。
- アーティキュレーションの統一:音の始まりや終わりのニュアンスを合わせることで、よりまとまりのある演奏が実現します。
特に、「音程」は常に意識を持ちましょう。部活動の場合、楽器を始めたばかりの子も一緒に演奏します。この「音程」がずれてしまうと、1人一人がうまく演奏できても、合奏ではまったくきれいに聴こえません。
日々の積み重ね、周りの音を聴き合わせることができるか、が演奏の良し悪しを決める大きなポイントとなります!
楽器ごとの練習の取り組み
楽器ごとの特徴を生かした練習も重要です。例えば:
- 管楽器:息のコントロールや音程の調整に特化した練習を行い、安定した音色を目指します。
- 打楽器:正確なリズムとダイナミクスの練習を通じて、曲の流れを支える役割を果たします。
- 弦楽器(必要な場合):音量のバランスを整え、アンサンブルの中での音響効果を高めます。
吹奏楽コンクールでの心構え
緊張への対処法
コンクール本番では、緊張によるミスを防ぐための心構えが重要です。深呼吸やストレッチを取り入れることで、身体の緊張を緩和できます。
また、リハーサルを本番同様の環境で行うことで、緊張への耐性をつけることができます。近くの市民ホールなどでの演奏して、全体のバランスをとることもポイントです。
筆者が所属していた部活も団体も、本番近くになると、市民ホールや音楽ホールを借りて、全体の音のバランスなどチェックをしました。
ステージを使用すると、本番を想定した演奏者同士の座る位置、入退場などもチェックできます。実施を強くおすすめします!
ポジティブなチーム精神の維持
吹奏楽は団体での活動が中心です。そのため、チーム内でポジティブな雰囲気を維持することが成功の鍵となります。
お互いを励まし合い、協力することで、より良い演奏が実現します。成功だけを目指すのではなく、音楽を楽しむ気持ちを忘れずに臨みましょう。
吹奏楽コンクールに挑戦した経験談
全国大会出場経験のある吹奏楽部員、佐藤美幸さん(仮名)にお話を伺いました。
準備段階での重要なポイント
「私たちの吹奏楽部では、毎日音程を合わせる練習をしました。特に合奏の際、指揮者の指示に従いながら全員で音のバランスを整える努力をしました。それが結果的に音楽的な完成度を高める要因となりました。」
本番での心構え
「本番では、何よりも曲の流れを楽しむことを心掛けました。緊張はしましたが、事前に行ったリハーサルと同じように演奏することで、安心感が得られました。」と佐藤さん。
コンクール後の振り返りと次への準備
コンクールが終わった後には、振り返りを行いましょう。演奏の成功点や改善点を記録し、次のコンクールへの準備を効率的に進めることができます。
審査員の審査表が確認でき、具体的に良かったところ、伸ばして欲しいところが書かれています。
指導者と共に課題を洗い出し、次に向けた計画を立てることが重要です。
まとめ
吹奏楽コンクールで成功するためには、計画的な練習とポジティブな心構えが必要です。パート練習や楽器ごとの特化練習を通じて技術を磨く一方で、音楽を楽しむ気持ちを持つことが結果につながります。
ぜひ、吹奏楽コンクールに挑戦し、チームの力を発揮してください。

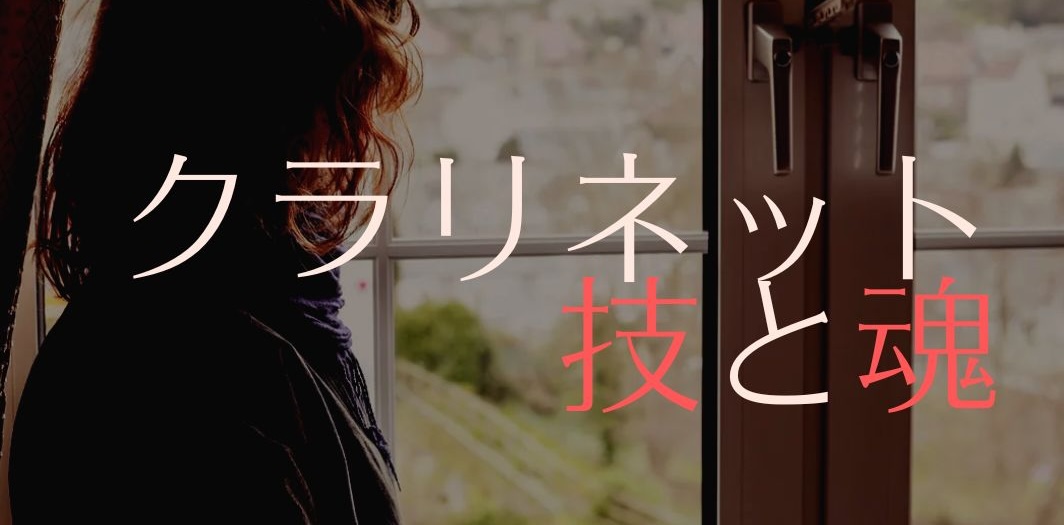

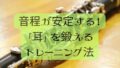
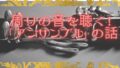
コメント