20年続けて見えてきたクラリネットの魅力
クラリネットは音楽を楽しむ手段であるだけでなく、人生において多くの教訓を与えてくれる存在です。20年以上クラリネットを続けてきて、私が感じていること、それがどのように日々の生活や人生観に影響を与えているかを振り返ります。
忍耐と努力の大切さを学ぶ
小さな進歩が大きな成果を生む
クラリネットを始めたきっかけは、中学入学後、吹奏楽部へ仮入部をしたことでした。仮入部1日目、私はフルート希望だったのですが、一緒に行った友人がクラリネット希望だったため、ついていくことに。
マウスピースをくわえ、息を吹くものの、なかなか音が出ず、大変苦労をしました。一緒に体験した子が4、5人いたように記憶していますが、音が出たのは一番最後、おそらく20分くらい、ただただふーふーと音を入れていたように思います。
その間、クラリネットパートの先輩たちが、あきらめることなく、優しく教えてくれました。その分、音が出たときの感動は大きく、今でも覚えています。周りの先輩たちが、「わぁ!」と拍手をしてくれたことを思い出します。
翌日、実はフルートへ行くつもりが、先輩たちに呼ばれるので、断れずそのまま毎日クラリネットを吹かせてもらうことに。入部後も、そのままクラリネットパートに配属されることになりました。
当時、吹奏楽部の人数が多かったため、最初の1ヶ月は、1年生はとにかく基礎練習。放課後の教室や、屋上で毎日音出し、基礎練習、時には体力作りのために学校内を走ったり、腹筋したりしたことも。
そんな毎日の練習を続け、最初に楽譜をもらった時、合奏したときは、とにかくたまらなく嬉しく、感動しました。この経験から、「日々の基礎練習」が「合奏の楽しさ」を生むことを学びました。
難しい楽曲への挑戦
初めて挑戦した難易度の高いクラシック楽曲は、途中で何度も挫折しそうになりました。しかし、焦らず、できない箇所を、メトロノームとにらめっこしながら、何度も何度も練習をしました。
諦めずに練習を続ける中で徐々に演奏できるようになった瞬間の達成感は、言葉では表せないほど大きなものでした。
仲間と音楽を奏でる楽しさ
アンサンブルから学んだ協調性
クラリネットはソロ演奏も魅力的ですが、アンサンブルや吹奏楽では他の楽器との調和が求められます。音を合わせ、リズムを共有する中で、相手を思いやりながら共に音楽を作り上げる喜びを学びました。
アンサンブルの経験は、個々の実力や演奏力を成長させるとても良い機会です。一人ひとりの音が曲の全体を通して、非常に重要になるためです。
共通の目標が生む絆
20年間で多くのコンサートや発表会に参加しました。そのたびに仲間と共に準備を重ね、目標を達成した瞬間に生まれる絆の強さを感じました。音楽を通じて得た仲間との繋がりは、人生の宝物と言えるでしょう。
自己表現の場としてのクラリネット
感情を音に乗せる喜び
日々の生活では言葉にできない感情を、クラリネットを通じて表現することができました。嬉しいときも悲しいときも、クラリネットの音色が自分の心の声を代弁してくれるような気がします。
私は、基礎練習、ロングトーンをする時が、一番心が落ち着きます。音に集中するからでしょうか。心を整える時間にもなっているように感じています。
独自のスタイルを築く自由
クラリネットの演奏には、演奏者ごとに独自のスタイルがあります。技術だけでなく、自分の個性や価値観を音に込めることで、より深い自己表現が可能になります。
それには、さまざまなタイプの曲にチャレンジすることをおすすめします。
クラリネットが教えてくれた人生の教訓
継続は力なり
20年間続ける中で、どんなに小さな一歩でも積み重ねることが重要だと気付きました。この考え方は、仕事や趣味、日常生活のあらゆる場面で役立っています。
曲を吹く時間がなくても、なるべく毎日10分でも基礎練習だけは続けるように意識をしています。基礎練習を数日休んでしまうと、なんとなく下手になっているように感じます。
逆に、直したい癖がある場合は、数日休み、正しい姿勢・くわえ方を意識し直すことができます。
音楽がもたらす癒しと喜び
クラリネットを演奏することは、自分自身だけでなく聴いてくれる人々にも喜びを与える力があると実感しました。その力を通じて、音楽が持つ癒しの力の偉大さを感じています。
まとめ:クラリネットがくれたもの
クラリネットを通じて得た経験や教訓は、私の人生を豊かにしてくれました。努力の大切さ、仲間との絆、自己表現の自由、音楽による感動など、多くの価値あるものをこの楽器から学びました。クラリネットを手にすることで、音楽を通じて人生を深く味わう喜びをこれからも追求していきたいと思います。

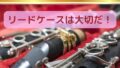

コメント