「新しい趣味として楽器を始めてみたい」「学生時代に部活を検討している」そんな方にこそ知ってほしいのが、吹奏楽バンドの世界です。
吹奏楽は、ただ音を合わせる活動ではなく、仲間と支え合いながら一つの作品を作り上げていく“共同体験”のようなものです。練習の積み重ねで育つ信頼、ステージに立った時の緊張と興奮、そして音楽が人の心に届く喜び。
この一連の経験が、吹奏楽ならではの大きな魅力と言えます。私自身、高校時代から社会人になった今まで吹奏楽に携わり、かけがえのない仲間や経験を得ることができました。
吹奏楽バンドの活動で得られるものとは?
音楽を通じた自己表現と成長
吹奏楽の魅力の一つは「自己表現の幅広さ」です。楽譜に書かれている音符は同じでも、吹き方や息遣い、アーティキュレーションの違いで、まったく異なる表現になります。
例えば、クラリネットなら柔らかく温かみのある音で心地よい旋律を届けることもできますし、逆に鋭さを持たせてリズムを力強く支えることも可能です。何度同じ曲を演奏しても、その時の気持ちや解釈によって響きが変わるのが吹奏楽の面白さです。
吹奏楽ならではの「役割の美学」
吹奏楽では「役割の美学」が大きな学びになります。華やかなメロディを奏でるトランペットやフルートに注目が集まりがちですが、その背後には中低音域で和音を支える楽器や、リズムを安定させる打楽器が欠かせません。
自分の音が目立たなくても、アンサンブル全体に欠かせない存在であると気づくことで、「縁の下の力持ち」としての誇りを持てるのです。この感覚は社会生活や仕事における役割意識にもつながり、人生を通じて活きてきます。
地域とのつながりと社会貢献
吹奏楽バンドの活動は、学校や練習場にとどまりません。地域の商店街イベントや介護施設での訪問演奏、地元の祭りや記念式典、さらには友人の結婚式といった特別なシーンでも活躍の場があります。
演奏を聴いた方に「音楽のおかげで元気が出た」「涙が自然と出てきた」と言われる瞬間は、演奏者にとって大きなご褒美です。自分の音が誰かの心を揺さぶり、社会とつながる実感を得られるのは、吹奏楽ならではの大切な体験です。
保護者や周囲の人との関わり
支えてくれる人の存在を忘れてはいけません。 学生の場合、送迎、楽器運搬など、保護者の支えがあってこそ続けられる活動でもあります。社会人バンドの場合、結婚後は家族の協力がないと、続けることが難しくなります。周囲の人への感謝の気持ちを持つことも、吹奏楽を通じて学べる大切なことです。
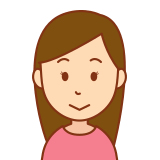
結婚後や出産後に趣味の活動をする場合は、家族への感謝がとても大切ですよ
団結力を育む
バント活動は、大人数で一つの音楽を作り上げる活動です。個人の技術向上だけでなく、他のメンバーと協力し、音楽を完成させるための団結力が求められます。このプロセスを通じて、チームの一員であることの達成感を味わえます。
音楽の多様性に触れる
吹奏楽バンドは、クラシックからポップス、ジャズまで幅広いジャンルの音楽を演奏します。コンクール参加する場合はクラシックを、自分たちで主催する演奏会や、依頼演奏では、クラシックだけでなくポップスやジャズと、演奏者側もさまざまな音楽を知り、楽しめます。多様な楽曲に触れることで、新たな音楽の魅力を発見でき、音楽の世界が広がります。
達成感を共有する
長い練習期間を経て挑むコンクールや定期演奏会は、日々の努力の集大成です。それは単なる演奏イベントではなく、仲間同士が汗を流し、時にはぶつかり合いながらも作り上げてきた成果そのものです。
本番で音がひとつになった瞬間、鳥肌が立つような感覚に包まれます。そして演奏後に仲間と目を合わせ「やりきったね」と笑い合える喜びは、他では得られない特別なものです。
人間関係の成長
部活動を通じて先輩・後輩、仲間とのつながりが生まれます。お互いに助け合う環境の中で、リーダーシップやコミュニケーション能力が育まれます。社会人の場合は、学生時代からの友人や仕事場とはまた違い、さまざまな年代、職種の人と出会える機会でもあります。
スポーツと違い、音楽は「現役期間」が長いので、OB・OG、地域の音楽愛好家との交流など、幅広い年齢層の方と出会える機会が多くあります。年齢や立場を超えて音楽でつながれるのは、かけがえのない経験です。
実際の吹奏楽部での体験談
高校時代から吹奏楽部に所属し、現在も音楽を楽しんでいる田部梨花さん(仮名)にお話を伺いました。
全員で作り上げた演奏会
「毎年の定期演奏会で、全員が一つになって音楽を作り上げる瞬間がとても楽しかったです。練習は大変でしたが、本番での達成感は何物にも代えがたいものでした。友人、そして家族から、聴きにきてもらえること、喜んでもらえることも、とても嬉しかったですね」と話してくれました。
筆者自身も、ホール、商業施設のステージ、結婚式場、ホテルロビーなど、さまざまな場所で演奏をする機会があります。特に社会人になってからは、仕事の時間とは別に自分たちの時間を使うなど、調整は大変ですが、メンバーと演奏できる喜びはとても大きいものです。
部活動での仲間との絆
「吹奏楽部で過ごした時間が、私の高校生活の中で一番の思い出です。仲間と一緒に音楽に向き合い、一緒に笑い、一緒に乗り越えた経験が今の私を支えています。」と、田部さん。
筆者も同感で、学生時代の思い出は、ほぼ部活と言っても過言ではありません。吹奏楽部は、春は入学式、夏に「コンクール」、秋には体育祭、冬には演奏会、その合間に依頼演奏など、文化部としては、結構イベントが多い部活です。
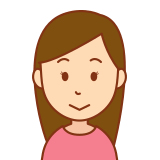
土日の練習も多いですし、長期休みはほとんど部活をしに学校に通っていました。それが苦にならないほど、毎日楽しく、今でも良い思い出です!
吹奏楽バンドの「四季」のイベント
学生の場合
- 春:新入生歓迎演奏・入学式演奏 新入生へアピールできる機会です。
- 夏:コンクールシーズン 吹奏楽は「夏」にコンクールを迎えます。緊張感と達成感が入り混じる、最も熱い時期。練習量も増え、仲間との絆が深まります。
- 秋:文化祭・体育祭での演奏 /アンサンブルコンクール 学校行事での演奏は、普段とは違う雰囲気で楽しめる貴重な機会。在校生に楽しんでもらえる曲目、構成を企画します。
- 冬:定期演奏会 一年の集大成。照明や演出にもこだわり、学校外の方も来てくれる機会です。観客に感動を届ける場です。
社会人バンドの場合
- 春〜夏:コンクールシーズン コンクールは、学生と違い練習時間の取りにくい社会人にとっては、仕事とプライベート、練習時間の調整に苦労をする時期でもあります。その苦労もあり、学生時代のコンクールとはまた違った達成感があります。
- 秋:アンサンブルコンクール クラリネット○重奏、木管○重奏、金管○重奏など小編成でのコンクールが秋に行われます。
- 冬:定期演奏会 社会人バンドにとって、家族や友人にも活動を見てもらえる晴れのステージ。演奏者としても思いっきり楽しみましょう。
吹奏楽バンドの活動を始めるには?
楽器選びと初期準備
吹奏楽部やバンド活動を始める際には、まず自分に合った楽器を選ぶことから始めます。初心者であれば、経験者や顧問の先生、楽器店に相談して、自分に合った楽器を選びましょう。
また、必要な機材の準備も忘れずに!楽器以外の必要機材は、チューナー、譜面台、メトロノーム、楽器メンテナンス道具などがあります。
仲間を見つける方法
吹奏楽部や地域の音楽サークルに参加することで、音楽の仲間を見つけることができます。音楽教室では、「バンドメンバー募集」なんて張り紙もありますね。ぜひ探してみてください。経験者から初心者OKや、「ママさんバンド」などお子様がいる方が参加しやすいバンドもあります。
まとめ
吹奏楽は「音楽活動」という枠を超え、人生そのものを豊かにしてくれる要素が詰まっています。技術の向上だけでなく、仲間と築く絆、地域社会との交流、そしてどんな困難にも立ち向かう粘り強さまで育ててくれるのです。
私自身、吹奏楽を通じて仲間と大切な思い出を作り、演奏を聴いてくれた人の笑顔を見ることで、続けてきて良かったと心から感じています。楽器を手にすれば、そこから「あなたの音楽の旅」が始まります。迷っている方も、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

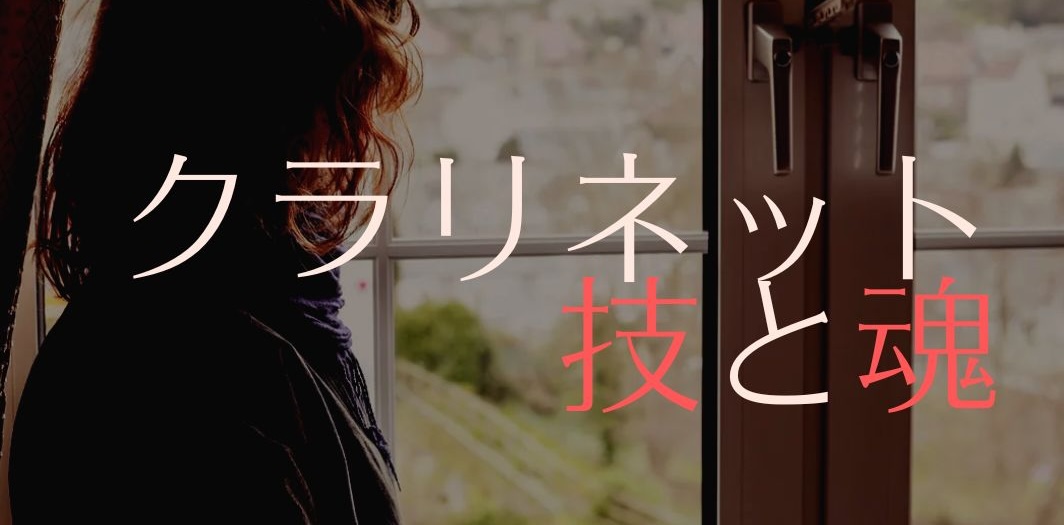
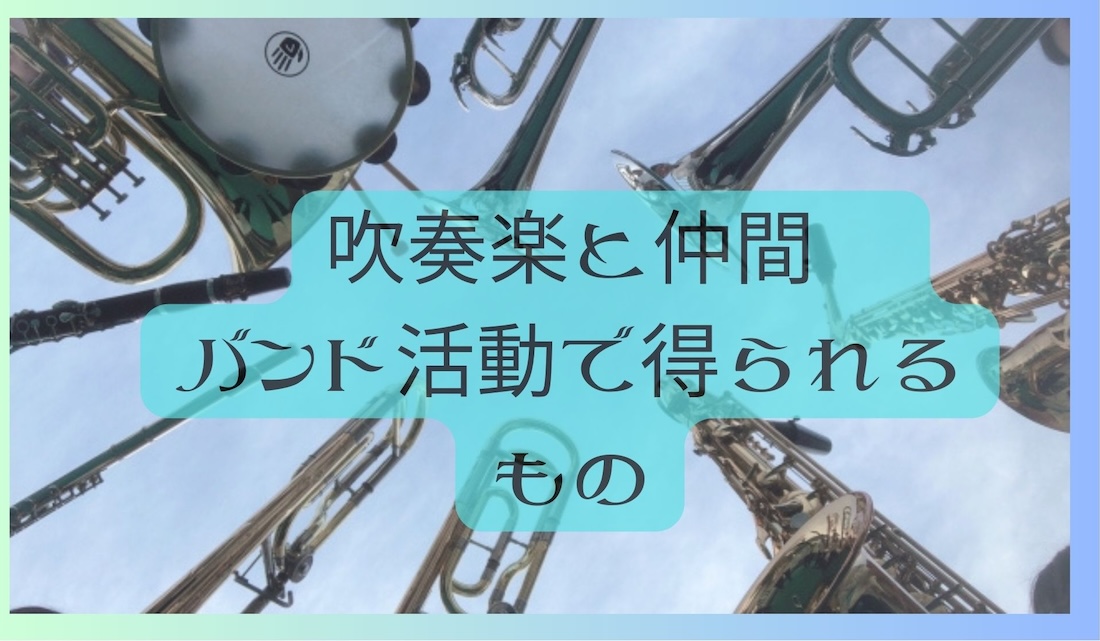

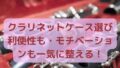
コメント