大切な楽器を長く、美しく保つために、メンテナンスはとても重要です。クラリネットは、木と金属、そして繊細なタンポ(パッド)で構成された、非常にデリケートな楽器です。演奏を重ねるほどに音色に深みが増す一方で、湿気や汚れ、温度変化に弱く、日々の手入れを怠ると音質の劣化や故障の原因になります。
私自身、中学生の頃からクラリネットを吹き続けてきましたが、楽器のコンディションが良いと、音の伸びや響きがまったく違うことを実感します。この記事では、演奏後に自宅でできる日常的なクリーニング方法と、長く愛用するための保管のコツを、筆者の失敗談も含めて、初心者の方にもわかりやすくご紹介します。
演奏後のルーティンケア(毎回行うべき基本)
クラリネットは木製ですから、この毎日のケアはしっかりと行うことを推奨します。
スワブで管内の水分をしっかり除去
演奏のたびに、クラリネットの内部には目に見えない水分が残ります。練習後にすぐ片付けてしまうと、翌日にはタンポがふやけて音がこもることもあります。私も部活時代にタンポが原因で急に音が出なくなり、先輩に助けてもらった経験があります。演奏後のスワブ掛けは、単なる作業ではなく楽器を守る“お礼”のような時間です。
演奏後は必ず分解し、スワブ(専用の布)を通して各管体の内側を丁寧に拭き取りましょう。スワブは無理に引っ張らず、引っかかりがないように注意。特に下管は水分が溜まりやすいため、念入りに行うのがポイントです。
スワブにはおもりの付いたヒモがついており、そのおもりを本体、マウスピースの太い方から入れて、逆側からおもりをひっぱって使用します。太い方から入れるのは、細い方から入れてしまうと、布の摩擦によって先端など傷つける可能性があるからだそうです。

YAMAHA クリーニングスワブM
超吸水加工を施したマイクロファイバー素材生地。 優れた吸水性能と四隅Rカットで滑らかな通し心地です。 両端の紐により反対側から引き戻しやすい構造。

ANFREE(アンフリー) モコモコクリーニングスワブ Bbクラリネット用
台湾のサクソフォンメーカー「アンフリー」の木管楽器用スワブ。モコモコした生地は吸水力抜群のマイクロファイバー製。ボリュームのある形状で管内にぴったりと密着。タンポの水分も適度に除去できるデザイン。
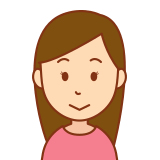
スワブを洗濯することも忘れないように!
私は週1で洗っています。
タンポ周辺の湿気チェック
練習後は、クリーニングペーパーをキーの下に差し込み、軽く押さえて数秒待ちましょう。こすったり引き抜くとタンポを傷めます。
タンポはキーの下にある白いパッドで、音孔を密閉する重要なパーツです。湿気が溜まるとベタつきや変形の原因になります。クリーニングペーパーをキーの下に挟み、軽くキーを押さえて水分を吸い取ります。タンポが不調になると、音程が安定しなくなったり、そもそも綺麗な音がでなくなってしまいます。タンポは消耗品で、一般的に以下のように推奨されています。
私は以前、力を入れすぎて皮を破ってしまい、修理に出す羽目になったことがあります。それ以来、ゆっくり作業するようにしています。
◯毎日数時間使用する場合:約半年
◯定期的な調整や日々の手入れ(水分除去など)を行う場合:2〜3年に1回の全体交換が推奨されるが、より長持ちすることもある
◯交換が必要なサイン:
- タンポの表面にシワが寄っている
- 中のフェルトが歪んでいる
- 表面の皮が硬くなっている/破れている
- 音漏れや音程の不安定さがある(タンポの密閉性が損なわれている)
中学生の頃、演奏会を数日後に控えたある日、練習中に、特定の音が急に出にくくなったことがありました。私が焦っていると、先輩が「タンポが割れたんじゃない?」と気づいてくれ、楽器を確認してくれました。
1箇所のタンポが割れており、すぐに先生に相談に行きました。演奏会は目の前、出られないのではないかと泣きそうになりました。先生が懇意にしている楽器店に連絡をすると、1日あればリペア可能とのことで、先生が楽器店まで持って行ってくれることになりました。
演奏後に、よく水分が溜まっているタンポだと気づいてはいたのですが、友人と話すことに夢中で、手入れを怠っていたことが原因だったと思います。それからは、時間がなくてすぐにできなくても、家に帰ったら手入れをするなど、注意をしています。
リードの乾燥と保管
リードは演奏時の“声帯”のような存在です。使用後のリードは水分を拭き取り、専用のリードケースに入れて乾燥させながら保管します。また複数枚をローテーションで使うと、リードの寿命も延びます。湿ったまま放置すると、カビや変形の原因になります。
私の場合、リードケースを使うようになってから寿命が倍近く伸びました。通気性のあるケースに入れ、数枚をローテーションして使うと安定した音色を保てます。
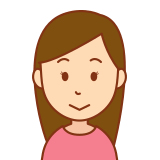
専用のリードケースを使用することをおすすめします
管体表面の拭き取り
演奏中に触れた部分には皮脂や汗が付着しています。ポリシングクロスで優しく拭き取り、金属部分のサビや木部の劣化を防ぎましょう。研磨剤入りの布は表面を傷つける恐れがあるため避けてください。
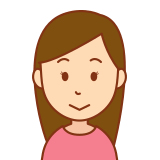
YAMAHAには、各楽器のお手入れセットがあります。初心者さんにおすすめ。
週1〜月1で行いたいメンテナンス
長く正常な状態で吹けるために行うメンテナンスをお伝えします。
マウスピースの洗浄
マウスピースは唇や呼吸が直接触れるため、汚れが溜まりやすい部分です。学生時代、数日放置して軽い異臭に驚いたことがあります。
それ以来、演奏後は常温水ですすぎ、ブラシで優しく洗うようにしています。お湯やアルコールは変形の原因になるので避けましょう。※熱湯やアルコールは変形の原因になるため使用しないでください。
ジョイント部分のグリスアップ
クラリネットは上下の管を差し込んで組み立てますが、その接合部(コルク)が乾燥すると、組み立てる時にスムーズに差し込めなくなってしまいます。差し込めないからと組み立て時に無理な力をかけてしまうと、コルクが裂けたり、管体が割れることも。
グリスはツヤが出る程度に薄く伸ばすのが目安で、月に1、2回のケアで快適な差し込みを維持できます。 薄く均一に塗布しましょう。
キーオイルで可動部を保守
キーの動きが重くなったり、キー同士が擦れる音が気になる場合は、専用のキーオイルを使って可動部に潤滑を与えます。綿棒や針付きオイラーで、必要な箇所にほんの少量だけ差すのがコツです。
保管のポイント
湿度と温度の管理
木製クラリネットは生きた木材のように、気候変化に反応し、湿度と温度の変化に非常に敏感です。湿度が低いと収縮して割れ、高いとタンポが劣化します。私の知人は冬場にベル部分に小さな亀裂を作ってしまいました。
それ以来、私は楽器を置いている部屋には、温度計と湿度計を置き、ケースには乾燥剤と加湿剤を、季節で使い分けています。
ケース内での安定保管
演奏後は必ず分解し、各パーツをスワブで乾燥させたうえでケースに収納します。ケース内でパーツが動かないよう、正しい位置に収めることが大切です。リードは別の乾燥ケースに入れて保管しましょう。
長期保管時の注意点
長期間演奏しない場合でも、月に一度はケースを開けて湿度を確認し、スワブで軽く拭き取るなどのケアを行いましょう。木部のひび割れやタンポの固着を防ぐことができます。
子どもを産んでからは、しばらく楽器を使用していませんでした。そのため楽器をクローゼットの中にしまっていたのですが、これが失敗でした。ケースがカビてしまったのです。
慌てて楽器店に持って行き、メンテナンスをお願いしました。幸いなことに楽器は無事でしたが、ケースは処分することに。温度・湿度には気を配りましょう!
おすすめお手入れアイテム一覧
筆者のおすすめお手入れアイテムをまとめました。
| アイテム | 用途 | 使用頻度 |
|---|---|---|
| スワブ | 管内の水分除去 | 毎回 |
| マウスピースブラシ | マウスピースの内部洗浄 | 毎回〜週1 |
| クリーニングペーパー | タンポの水分吸収 | 週1〜月1 |
| コルクグリス | ジョイントの気密保持 | 月1〜2回 |
| キーオイル | キーの可動部メンテナンス | 月1〜2回 |
| ポリシングクロス | 管体表面の汚れ拭き取り | 毎回 |
| 湿度計・乾燥剤 | 保管環境の管理 | 常時 |
| リードケース | リードの乾燥・保管 | 毎回 |
まとめ
クラリネットの手入れは、演奏者と楽器が信頼関係を築く時間です。音が出にくい、キーの動きが鈍い、リードが響かない——そんな小さな変化に気づけるのも、日々のケアを通じて楽器と向き合っているからこそ。
「今日はよく鳴ってくれたな」 「ちょっと湿気が多いかも」そんなふうに、クラリネットと心を通わせる時間が、演奏の質を高め、音楽をもっと豊かなものにしてくれます。
拭き取りや注油を通じて、音が生き返る瞬間を感じることができます。思うように吹けない日こそ、優しく磨いてあげてください。その積み重ねが、あなたの音色に深みを与えてくれます。
ぜひ、今日からの演奏後に、ほんの5分だけでも丁寧なクリーニングを取り入れてみてください。クラリネットは、きっとその気持ちに応えてくれるはずです。

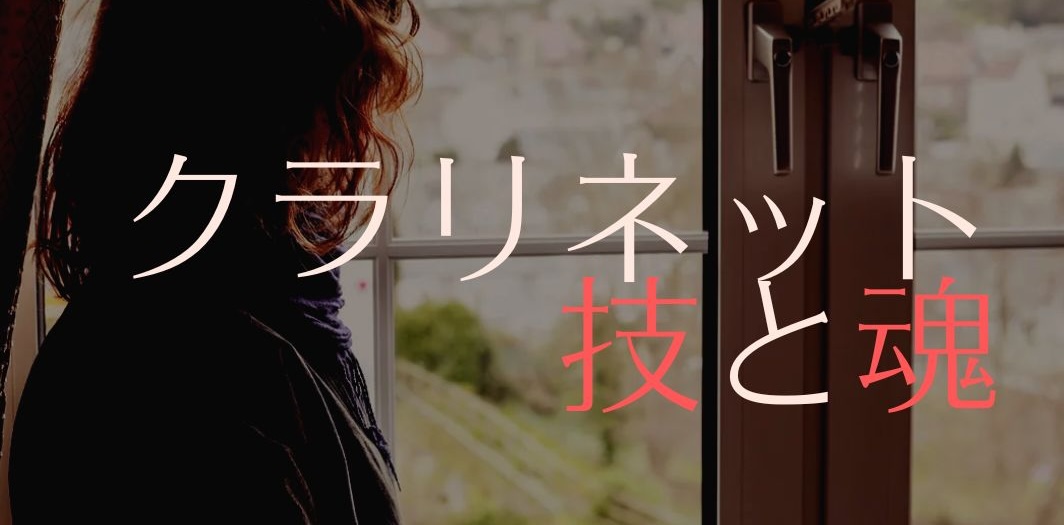
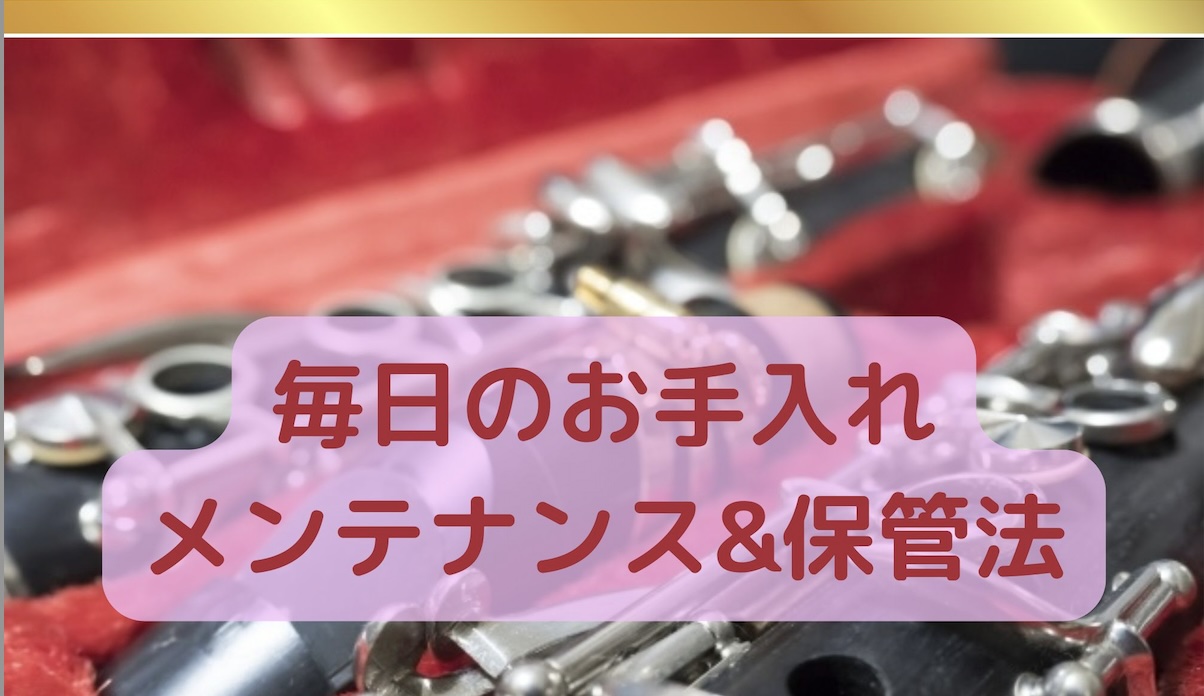

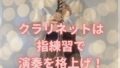
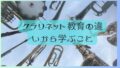
コメント